「扇の的(平家物語)」現代語訳・原文・あらすじを簡単に解説
中学2年生国語で学習する「扇の的(平家物語)」の現代語訳・原文・あらすじ、那須与一について、定期テストで必要なポイントである内容の解説・古語の意味・現代仮名遣いや表現技法、係り結びなどをわかりやすく解説するよ。
「扇の的(平家物語)」解説
平家物語とは
「平家物語」とは、鎌倉時代に成立した「軍記物語(ぐんきものがたり)」。軍記物語は、実際にあった合戦(かっせん)をテーマにした文学のことだよ。
琵琶法師(びわほうし)によって語り継がれて、平氏が栄華を極めたときから、源氏に敗れて滅びるまでが描かれているよ。
「平家物語(祇園精舎の鐘の声)」でも学習したね。
「扇の的」とは
「扇の的」はそんな「平家物語」の第十一巻に書かれている「那須与一」と「弓流」のエピソード部分なんだ。
描かれているのは、源平合戦の戦いのひとつである、1185年に起きた「屋島の戦い」でのこと。
京都や一の谷などで源氏に敗れた平氏は、香川県の屋島というところにたどり着くよ。でも、そこでも義経の奇襲に合ってしまい、慌てた平氏は舟で海上に逃げたんだ。
源氏は陸にいて、平氏は船で海の上にいる状態でお話は始まるんだ。
「扇の的(平家物語)」那須与一とは
那須与一(なすのよいち)は、下野国(現在の栃木県)出身の鎌倉時代の武士。
屋島の戦いでは、源氏側として戦っているよ。
「扇の的」でも、見事扇に矢を命中させたように、かなりの「弓の名手」として有名だったんだ。
ただ、この那須与一、いろいろな伝説を持ってはいるけれど、実際にいたかどうかはハッキリしないんだ。※実在はしないけれど、モデルがいたとも言われているよ。
「扇の的(平家物語)」あらすじ
「扇の的」 あらすじ
※色のついた言葉はクリックすると意味が表示されるよ。 ときは平安時代。平安時代の有力な武士の一族。平清盛(たいらのきよもり)などが有名。平家と平安時代の有力な武士の一族。鎌倉幕府をひらいた源頼朝などが有名。源氏の戦いは源氏の優勢となり、追いつめられた平家は舟で海の上へ。
海の平家と陸の源氏で向かい合っていた。やがて平家の天皇や貴族、有力な武家のもとに仕える女性の使用人のこと。女房が扇を竿の先につけて、舟の端のほうへ立て、手招きをした。 「この扇を矢で射って落とすことができるか」という源氏への挑発だった。 源氏の大将である源頼朝の弟で、この時の戦いでは源氏の大将をつとめていた。義経は、那須与一にその挑戦を受けるよう命令する。 激しい風と高波の中、常に揺れ動く扇。 扇を射ることができなかった場合は、腹を切る覚悟でのぞむ与一。
みごと扇を射落としたのであった。 感心する平家。ほめたたえる源氏。 そのあまりのおもしろさに平家の男がひとり、扇のあった場所で舞を舞った。 その男のことも射るように那須与一に命令が下る。 与一が男も射倒すと、平家のものたちが静まりかえる中、源氏はまた歓声をあげた。 「よく射た」と言うものもあれば、
「心ないことを」と言うものもあった。 源氏のこの行為に、平家が攻め入ると、源氏も馬ごと海に乗り入れ戦った。 このとき、大将の義経の弓が平家によって海へ落とされてしまった。 味方がとめるのも聞かず懸命に弓を拾いあげた義経に、「弓よりもお命が大切」と年をとった家来のこと。老臣たちが非難する。 「こんな弱々しい弓を敵が拾い、大将義経がこのような弓を使っていると笑われないように命懸けで拾ったのだ」と義経は言い、皆は感心するのだった。
「扇の的(平家物語)」原文
「扇の的」原文
ころは二月十八日の現在の午後6時。酉の刻ばかりのことなるに、をりふし北風激しくて、磯打つ波も高かりけり。舟は、揺り上げ揺りすゑ漂へば、扇もくしに定まらずひらめいたり。沖には平家、舟を一面に並べて見物す。陸には源氏、馬の口に含ませて、手綱をつけるための金具の部分のことt。くつばみを並べてこれを見る。いづれもいづれも晴れならずといふことぞなき。与一目をふさいで、 「南無弓矢の神様と仏教の菩薩さまを一つのものとして信仰していた。八幡大菩薩、我が国の神明、栃木県日光市にある二荒山神社の神様のこと日光の権現、栃木県宇都宮市にある二荒山神社の神様のこと宇都宮、栃木県那須郡那須町にある湯泉神社の神様のこと那須の湯泉大明神、願はくは、あの扇の真ん中射させてたばせたまへ。これを射損ずるものならば、弓切り折り自分で命を絶つこと自害して、人に二度面を向かふべからず。いま一度本国へ迎へんとおぼしめさば、この矢はづさせたまふな。」 と心のうちに祈念して、目を見開いたれば、風も少し吹き弱り、扇も射よげにぞなつたりける。 与一、戦いを始めるときの合図などに使われる矢で、音を立てて飛ぶように出来ている。かぶらを取つてつがひ、よつぴいてひやうど放つ。小兵といふぢやう、「束」は一握りの幅で、指4本分。「伏」は指一本分の幅のこと。普通の矢の長さは十二束だったといわれている。十二束三伏、弓は強し、浦響くほど長鳴りして、あやまたず扇の要ぎは現在の約3センチ。一寸ばかりおいて、擬音のひとつ。矢が風を切って的に当たった音をあらわしている。ひいふつとぞ射切つたる。かぶらは海へ入りければ、扇は空へぞ上がりける。しばしは虚空にひらめきけるが、春風に一もみニもみもまれて、海へさつとぞ散つたりける。夕日の現在は「かがやく」だが、当時は「かかやく」と発音していた。かかやいたるに、みな紅の扇の日出だしたるが、白波の上に漂ひ、浮きぬ沈みぬ揺られければ、沖には平家、船端をたたいて感じたり、陸には源氏、矢を入れる道具のこと。腰や肩にかけていた。えびらをたたいてどよめきけり。 あまりのおもしろさに、感に堪へざるにやとおぼしくて、舟のうちより、年五十ばかりなる男の、黒革をどしの鎧着て、白木(塗料を塗っていない、皮を削っただけの地のままの木材)で作られた柄(刀の手で握るところ)のこと。または、白い糸を巻いた柄のこと。白柄の長刀持つたるが、扇立てたりける所に立つて舞ひしめたり。義経に仕えていた重臣伊勢三郎義盛、与一が後ろへ歩ませ寄つて、 「御命令ということ。この場合、「義経からの命令だ」ということ。御定ぞ、つかまつれ。」 と言ひければ、今度は戦闘用の矢のこと。「えびら」の中の上差のかぶら矢の次に差してある。中差取つてうちくはせ、よつぴいて、しや頸の骨をひやうふつと射て、舟底へ逆さまに射倒す。平家の方には音もせず、源氏の方にはまたえびらをたたいてどよめきけり。 「あ、射たり。」 と言ふ人もあり、また、 「情けなし。」 と言ふ者もあり。 (中略) 「弓の惜しさに取らばこそ。義経が弓といはば、二人しても張り、もしは三人しても張り、叔父の義経の叔父である、源為朝のこと。弓矢の名手で、強弓(張りが強くて、引くのに力がいる弓のこと)の使い手として有名だったといわれている。為朝が弓のやうならば、わざとも落として取らすべし。尩弱たる弓を敵の取り持つて、『これこそ源氏の大将九郎義経が弓よ。』とて、嘲哢せんずるが口惜しければ、命にかへて取るぞかし。」 と、宣へば、みな人これを感じける。
「扇の的(平家物語)」現代語訳
時は二月十八日の午後六時くらいのこと、ちょうど北風が激しくて、海の波打ち際に打つ波も高かった。船は、上に揺れ下に揺れ漂って、扇も竿に止まらずに動いている。
沖には平家が、船を一面に並べて見物している。
陸には源氏が、馬のくつわを並べてこれを見ている。
どちらもどちらも晴れ晴れしないということはない。
与一は、目を閉じて、「南無八幡大菩薩、私の故郷の神様、日光の仏様、宇都宮、那須の湯泉神社の神様、どうか、あの扇の真ん中を射させてくださいませ。これ(射るのを)を失敗してしまったら、弓を切り折り自殺して、人に再び顔を合わせることはない。いま一度(私を)故郷に迎えようとお思いになるならば、この矢を外させないでください。」と心の中で祈念して、目を見開くと、風も少し吹き弱まり、扇も射やすくなった。
与一は、かぶら矢を取ってつがえて、十分に引っ張って、ひょうっと放った。
(与一は)小兵とは言いながら、(矢は)十二束と三伏の長さで、弓は強く、(与一が放った矢は)浦に響くほど長く鳴って、間違うことなく扇の真ん中の三センチくらい離れた所を、ひいふっと切り離した。
かぶら矢は海に落ち、
扇は空へ舞い上がった。
(扇は)しばらくの間空にひらひらと舞っていたが、春風に一もみ二もみもまれて、海へさっと散り落ちた。
夕日が輝いているところに、真っ赤な扇で太陽が描いてあるの(扇)が、白い波の上に漂って、浮いたり沈んだり揺れている(のを見て)、沖には平家が、船端をたたいて感動し、
陸には源氏が、箙(えびら)をたたいてどよめいた。
あまりのおもしろさに、感動をがまんできなかったと思われて、船の中から、年が五十くらいの男で、黒革おどしの鎧を着て、白柄のなぎなたを持った(平家の)男が扇の立ててあった所に立って舞を踊った。
伊勢三郎義盛が、与一の背後に(馬を)歩ませてきて、「(義経の)ご命令である、射よ。」と言ったので、(与一は)今度は、中差を取り出して、弓につがえて、十分に引っ張って、(男の)首の骨を、ひょうふっと射て、船底へ逆さまに倒した。
平家方は静まり返っていて、
源氏方は、今度も箙をたたいてどよめいた。
「あぁ、よく射た。」と言う人もいた、また、
「心ないことを。」と言う人もいた。
(中略)
「弓が惜しくて、取ったのではない。(私)義経の弓が、二人がかりで(弦を)張る、もしくは三人がかりで(弦を)張る、叔父の源為朝の弓のようであるならば、わざとでも落として、敵に取らせる。」
(けれども)弱々しい弓を敵が拾って、「こんなものが、源氏の大将の、九朗義経の弓だとよ。」と言って、馬鹿にされ笑われるのが、悔しいので、命に代えても、拾ったのだよ。」とおっしゃれば、みんなこれを聞いて感動した。
「扇の的(平家物語)」歴史的仮名遣い
歴史的仮名遣いとは、今の日本で普通に使われている「現代仮名遣い」に比べて「古い」仮名遣いのことだったね。
カンタンに言うと、現代とは違う「かな文字」の使い方ということ。
テストでは、この歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直さなくていけない問題が出たりする ので、よくチェックしておこう。
歴史的仮名遣いを現代語になおすときのルールについて解説しているページもあるので、参考にしてね。
| 歴史的仮名遣い | 現代仮名遣い |
|---|---|
| にんぐわつ(二月) | にんがつ |
| をりふし | おりふし |
| 揺りすゑ | 揺りすえ |
| 漂へば・漂ひ | 漂えば・漂い |
| いづれも | いずれも |
| いふことぞなき | いうことぞなき |
| にっくわう(日光) | にっこう |
| だいみやうじん(大明神) | だいみょうじん |
| 願はくは | 願わくは |
| 射させてたばせたまへ | 射させてたばせたまえ |
| 向かふべからず | 向こうべからず |
| 迎へん | 迎えん |
| 矢はづさせたまふな | 矢はずさせたもうな |
| なつたりける | なったりける |
| 取つてつがひ | 取ってつがい |
| よつぴいてひゃうど放つ | よっぴいてひょうど放つ |
| こひやう(小兵)といふぢやう | こひょうというじょう |
| 要ぎは | 要ぎわ |
| ひいふつとぞ射切つたる | ひいふっとぞ射切ったる |
| 海へさつとぞ散つたりける | 海へさっとぞ散ったりける |
| ぐれなゐ(紅) | ぐれない |
| 堪へざるにやと | 堪えざるにやと |
| をのこ(男) | おのこ |
| をどしのよろひ(鎧) | おどしのよろい |
| 長刀持つたるが | 長刀持ったるが |
| 立つて舞ひしめたり | 立って舞いしめたり |
| いせのさぶらうよしもり(伊勢三郎義盛) | いせのさぶろうよしもり |
| 寄つて | 寄って |
| ごぢやう(御定) | ごじょう |
| 言ひければ | 言いければ |
| うちくはせ、よつぴいて | うちくわせ、よっぴいて |
| しや頸の骨をひやうふつと射て | しゃ頸の骨をひょうふっと射て |
| 言ふ人もあり・言ふ者もあり | 言う人もあり・言う者もあり |
| 義経が弓といはば | 義経が弓といわば |
| おぢ(叔父) | おじ |
| 弓のやうならば | 弓のようならば |
| わうじやく(尩弱) | おうじゃく |
| 持つて | 持って |
| 大将くらう(九郎)義経 | 大将くろう義経 |
| てうろう(嘲弄) | ちょうろう |
| 口を(惜)しければ | 口おしければ |
| 命にかへて | 命にかえて |
| 宣へば | 宣えば |
「扇の的(平家物語)」古語の意味
「扇の的」が書かれている「平家物語」は、とても古い作品なので、今ではあまり使わない言葉や、難しい言葉が使われているよ。
テストでは、言葉の意味を答えなくてはいけない問題も出るので、ひとつひとつ確認しよう!
※「扇の的」の中で使われている意味を紹介しているので注意してね。
| 古語 | 意味 |
|---|---|
| 酉の刻 | 「とりのこく」。午後六時ごろのこと |
| をりふし | 「おりふし」。 折から。「ちょうどそのとき」というイメージ 【本文】をりふし北風激しくて |
| くつばみ | 馬の口につけて、手綱を取りつける金具のこと |
| 南無八幡大菩薩 | 弓矢の神様 |
| 神明 | 神様 |
| 日光の権現 | 与一の故郷である栃木県の神様 |
| 宇都宮 | 与一の故郷である栃木県の神様 |
| 那須の湯前大明神 | 与一の故郷である栃木県の神様 |
| たばせたまへ | 「たばせたまえ」。 漢字だと「賜ばせ給へ」。「なさってください」という意味で、強い尊敬が表されている。神様にお願いしているので、尊敬の言葉を使っている。 【本文】扇の真ん中射させてたばせたまへ。 |
| 面を向かふ | 「おもてをむかう」。 「面と向かう」つまり、正面から向かい合うこと。 扇を射ることができなかったら、自害して、もう二度と人には正面から向かい合うようなことはない(この世から姿を消す)、という与一の覚悟がこめられている。 【本文】人に二度面を向かふべからず。 |
| べからず | すべきでないという、禁止・できないの意味。 |
| おぼしめさば | 「思し召す(おぼしめす)」は、「お思いになる」という尊敬語。 |
| はづさせたまふな | 「はづす(外す)」、「たまふ(たまう」は「~してください」、「な」は「するな」という意味なので、「外させないでください」となる。 |
| 射よげに | 「よげ」は漢字だと「良げ」とか「善げ」となり、つまり「良い」という意味。「扇を射るのに良い」ということ。 【本文】扇も射よげになつたりける |
| かぶら | 戦いを始める合図に使ったりする、音を立てて飛ぶ矢。 |
| つがひ | 「つがい」。矢を弓の弦にかけること。 |
| よつぴいて | 「よっぴいて」。 漢字だと「能っ引く」と書く。弓を十分にひきしぼるという意味。 【本文】よつぴいてひやうど放つ。 |
| 小兵 | 「こひやう(こひょう)」。 体の小さい兵のこと。与一は、体が小さい(弓を引く力が弱い)とはいえ、矢の長さが十二束三伏もあって、弓も強いので・・という意味。 【本文】小兵といふぢやう・・・ |
| いふぢやう | 「いうじょう」。言うものの。 |
| 十二束三伏 | 「一束」は指4本分の幅、「一伏」は指一本分の幅。 |
| 長鳴りして | 長いうなりをたてて。与一の射った矢が長いうなりを立てて扇に向かって飛んでいる様子。 【本文】浦響くほど長鳴りして |
| あやまたず | 「あやまつ」は漢字だと「過つ」。つまり、過ちをおかすこと。 「あやまたず」とは、過ちをおかさないという意味なので、ここでは与一の矢が失敗することなく扇へ向かって射落とすことができた、ということ。 【本文】あやまたず扇の要ぎは… |
| 要ぎは | 「要ぎわ」。扇の根元にある軸の部分。「ぎわ」は「際」で、「すぐそば」という意味。 |
| 一寸 | 昔使われていた長さを表す単位。訳3.03センチメートル。 |
| 虚空 | 「こくう」。何もない空間。空中や大空のこと。 【本文】しばしは虚空にひらめきけるが |
| みな紅 | 「みなぐれない」とは、漢字で書くと「皆紅」となり、「すべてが紅色ということ。 【本文】みな紅の扇の日出だしたる |
| 船端 | 「ふなばた」。つまり、舟の端のほうのこと。 【本文】ふなばたをたたいて感じたり |
| 感じたり | 感嘆すること。与一がみごと扇を射ることができたので、平家の人々も感嘆している。 【本文】ふなばたをたたいて感じたり |
| えびら | 矢を入れて、背中に背負う道具のこと。 |
| どよめく | 大声をあげて騒ぐこと。 【本文】えびらをたたいてどよめきけり |
| 感に堪へざる | 「感」とは、感動のこと。「堪へざる」は「堪えることができない」、つまりがまんできないということ。 与一がみごと扇を射ることができたのを見て、感動してがまんできなくなった思われる男が舞を舞ったということ。 【本文】感に堪へざるにやとおぼしくて |
| おぼしくて | (そのように)「思われる」という意味。 【本文】感に堪へざるにやとおぼしくて |
| をどし | 「おどし」。 漢字で書くと「縅」。鉄や革で作った小さな板(札:さね)を糸や革ひもでつづり合わせたもの。鎧の一部。 |
| 御定 | 御命令 |
| つかまつる | 「…してさしあげる」という意味。現代語訳を見て「つかまつれ=射よ」という意味だと誤解しないように注意。 「御定」は御命令という意味で、伊勢三郎義盛が主君の義経に対して尊敬の意味を込めた言葉。それに対して、「つかまつれ」は伊勢三郎義盛が与一に対して、「してさしあげろ」と謙譲(へりくだること)の意味を込めた言葉。 何を「してさしあげろ」なのかというと、つまりは「男のことを射れ」という意味になる。 【本文】御定ぞ、つかまつれ |
| 中差 | 戦い用の矢。 |
| うちくはせ | 「うちくわせ」。 漢字だと「打食わせ」。矢を弓にしっかりとつがえること。 【本文】中差取つてうちくはせ |
| しや頸 | 「しゃくび」。 「しゃ」は接頭語で、「首」をののしっていう言葉。「ののしる」とは、悪口を言うこと。 つまり、源氏にとっては平家の男は敵なので、男の首のことを「しゃ首」とののしっている。 【本文】しゃ頸の骨を |
| 情けなし | 現代の「情けない」とは意味が違うので注意。 「思いやりがない」とか「薄情」という意味。 舞を舞った男の首を与一が射ってしまったので、「心ないことをするものだ」という意味を込めている。 【本文】「情けなし。」と言ふ者もあり。 |
| 為朝 | 「源為朝(みなもとのためとも)」。頼朝・義経の叔父。身長が2メートルを超える巨体で、気性が荒かったと言われている。そのため、為朝の使っていた弓も剛弓だった。 |
| 尩弱 | 「わうじゃく(おうじゃく)」。弱々しい様子。 |
| 源氏の大将九郎義経 | 九郎義経とは、源義経のこと。九男だったため、このように呼ばれた。この合戦での源氏側の大将。 |
| 嘲哢 | 「てうらう(ちょうろう)」 |
| 口惜し | 悔しい |
| ぞかし | ~なのだよ。文末に用いて、強く判断したものに、さらに念を押す意味を付け加える。 |
| 宣へば | 「のたまえば」。 |
「扇の的(平家物語)」内容のポイント
どんな様子が書かれているのか。誰が何をしているのか。なぜそうしたのかなど、場面の内容や人物の心情を読み取れるようにしよう。
とくにテストでよく出るところをひとつずつ確認していくよ。
「酉の刻」とは
昔は、十二支を使って時刻や方角を表していたんだ。
24時間を「子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)」の十二支で表すので、ひとつの動物ごとに2時間が割り当てられているよ。
なので、「酉の刻」とは、午後六時頃のことになるんだ。
テストでは、酉の刻が何時をさすのか?という問題が出ることもあるので、注意しよう。
「扇もくしに定まらずひらめいたり」とは
平家の女房が、扇を竿の先につけて、「この扇を矢で射ることができるか?」と挑発してきている場面だね。
那須与一という男がこの挑戦を受けることになったね。
那須与一が受けた挑戦の内容は?
【ミッション】
海に浮かぶ舟の端に立てられた竿の先についた扇を射落とせるか?
【難関ポイント】
- 馬に乗ったまま矢を放つ
- 風が激しく、波も高いので扇がつねに動く
- 扇までの距離なんと約72メートル
- 春先(※)の夕方6時なので、視界がハッキリしない
- 平家と源氏から注目されてプレッシャーMAX
- 義経からの命令なので失敗は許されない
※…二月十八日とあるけれど、これは旧暦で数えた場合で、新暦では三月二十一日にあたるので、春先になる。
このとき、北風が激しく吹いて波も高かったので、舟は上下に揺れていたんだ。
舟の端に立てられた竿の先についている扇だって、もちろん一緒に上下に揺れるよね。
問題例
「扇もくしに定まらずひらめいたり」とあるが、それはなぜか?
答え:北風が激しく吹いて波が高く、舟が上下に揺れて漂っていたから
古文から抜きだす場合:「をりふし北風激しくて、磯打つ波も高かりけり。舟は、揺り上げ揺りすゑ漂へば」の中から、問題文で指定された字数に合わせて抜きだす。
「晴れならずといふことぞなき」とは
「晴れ」とは、「晴れがましい」という意味で、気持ちが晴れているとか、得意げとかという意味。
「晴れならず」で「晴れがましくない」、
「…といふことぞなき」で「…ということはない」。
つまり、「晴れがましくないということはない」となって、結局は「晴れがましい」ということ。
扇を射ようとしている那須与一のことを、海の上の平家も、陸の上の源氏も注目しているよね。
これは与一にとって、「平家と源氏、どちらを見ても自分に注目している。晴れがましい気分だ」と感じたということだね。
「人に二度面を向かふべからず」とは
これは、扇を射ることができますように、とたくさんの神様にお願いをしている与一のセリフのひとつだね。
「もし射ることができなかったら、私は弓を折って、腹を切って、もう二度と人の前にはあらわれることはないでしょう」という意味なんだ。
失敗したら、死を覚悟するくらい、与一は真剣なんだね。
この時代の武士というのは、「恥をかくくらいなら死を選ぶ」という生き方をしてきたからね。与一が失敗するということは、源氏が平家の前で恥をかくということ。
なおさら、「自分が死んで責任を取る」くらいのつもりになるね。
「いま一度本国へ迎へんとおぼしめさば」とは
「本国」とは、その人が生まれ育った国のこと。
「扇の的」は、平家と源氏が戦った「屋島の戦い」でのひとコマなんだ。
「屋島」は、現在の香川県だよ。那須与一は下野国(現在の栃木県)の出身だよね。
つまり、故郷から遠くはなれた土地で戦いに参加していたということだね。
矢を射るとき、那須与一は心の中で神様にお願いをしていたね。
「南無八幡大菩薩」は、弓矢の神様。
「日光の権現」「宇都宮」「那須の湯泉大明神」は、与一の故郷である栃木県の神様なんだ。
「私をもう一度故郷へ迎えてもよいと思ってくださるのであれば」と、故郷の神様にお願いをしているんだね。
「扇も射よげにぞなつたりける」とは
神様に祈りをささげた与一が目を開くと、なんと激しかった風が少し弱くなっていた。
「このくらいの風なら、扇も射やすくなったぞ」、ということだね。
与一が射った矢①は?
与一が最初に放った矢は、「かぶら矢」というもの。
戦いを始める合図に使ったりするもので、音を立てて飛ぶ矢なんだ。
扇を射落とせばいいだけなんだから、かぶら矢で十分ということかな?
「小兵」とあるように、与一は体の小さい男性で、弓を引く力も弱いんだ。
でも、与一の使ったかぶら矢は「十二束三伏」の長さ。
普通の矢は、「十二束」なんだって。
「1束」は指4本分の幅、「1伏」は指一本分の幅だよ。
普通のよりも「三伏(指3本分の幅)」長いということだね。
さらに弓も強いものを使っていたので、矢は浦一帯に鳴り響くほど長いうなりを立てて飛んでいったんだね。
与一が射った矢①
矢の種類:かぶら矢(音のなる合図用)
矢の長さ:十二束三伏
弓も強いので、長いうなりを立てて飛んだ
標的:平家の舟の端の竿についた扇
結果:扇の要から一寸(約3㎝)離れたところを射切った
結果②:かぶら矢は海へ落ち、扇は空へと舞い上がった
「 みな紅の扇の日出だしたる」とは
「みな紅」の扇は、全て紅色に塗られた扇のこと。
「日出だしたる」は、その扇の真ん中に、金色の日の丸が描かれていることをあらわしているよ。
「夕日のかかやいたるに」とは、夕日が輝いている様子のこと。この「扇の的」のエピソードは、酉の刻(現在の夕方6時ごろ)のお話だからね。
夕日が輝いている中、白い波の上に、金色の日の丸が描かれた真っ赤な扇が漂って、浮いたり沈んだりしている様子を描いているんだね。美しい情景が伝わってくるね。
「夕日(赤)」「みな紅の扇(紅)」「日の丸(金)」「白波(白)」というように、色が効果的に使われていて、読み手に美しい情景を思いおこさせているんだね。
平家の男が、舞った理由は?
どうして平家の男は舞を舞ったのか? 理由が分かる部分を古文(原文)から見つけなさい。という問題も出ることがあるよ。
男は、 与一の見事な弓の腕に感動して、褒め称えるために舞ったんだよね。
与一が射った矢②は?
与一は扇を射切ったあと、もう一度矢を放っているよね。
今度の標的は…そう、平家の男だね。
与一がみごとに扇を射切ったことに感動した平家の男が、舟の中から出てきて、扇があった場所で舞を舞い始めたんだよね。
これは、与一のみごとな腕前をほめたたえるために、舞を舞ったとか、平家は政治の世界でも力を持っていて、貴族のような生活をしていたので、感動を舞であらわそうとしたのではないか、という考えがあるよ。
しかしなんと、源氏の大将である義経は、この舞を舞っている男のことも矢で射るように命令したんだ。
どうして?
与一のことをほめるために舞っているのに…
平家は貴族的な生活をしていたかもしれないけれど、源氏はずっとその影で悔しい思いをしてきた歴史があるから、カンタンに言えば「戦いの場でのんきに舞うなんて、イラッとした」のではないかという考えがあるよ。
そもそも、義経は平治の乱の後、山中や東北で育ったので、平家の人間のようい雅(みやび)なことに対しての理解や関心がなかった可能性も考えられるね。
なので、老武士の踊りを見ても、「ほめたたえている」というよりも、「馬鹿にしている」と受け取ってしまったのかもしれないね。
命令を受けて、「男を射殺そう」と覚悟を決めた与一が、「戦い用」の中差の矢を使ったところも注目しておこう。
「源平盛衰記」に書かれている裏話
「源平盛衰記」という作品には、この「扇の的」の裏話が少し書いてあるよ。
①平家が扇を射るよう挑発した理由
この時代、平家の一族には天皇になっている人もいたよね。
「紅い扇」に「金色の日の丸」というのは、現在の「天皇旗」のデザインに似ているよね。
実際、この扇は高倉院が厳島神社に奉納したものなんだ。
源氏から逃げていた平家が厳島神社に寄ったときに、この扇を渡されて、「この扇の前では矢は射った本人に戻ります」と言われたとのことだよ。
つまり、源氏に追い詰められてしまった状況をひっくりかえす「カケ」みたいな気持ちもあって、扇を掲げたんだ。
「天皇ゆかりの扇を、射れるもんなら射ってみなさい」という挑発でもあったとも書かれているよ。
さすがに天皇ゆかりの扇の真ん中(日の丸)を射抜くのはやめておこうと思ったから、与一も、扇の「要」の部分を射切ったんだね。
②平家の男を射った理由
「あ、射たり」と言う人もあれば、「情けなし」と言うひともあったと書かれているように、源氏の中でも「射るべきだ」と「射るのはやめておこう」という二つの意見で分かれたんだ。
でも、これはあくまで本気の戦い。
相手がスキを見せたのなら、一人でも確実に倒しておくべきだ、という考えで射ることにしたと書かれているよ。
与一が射った矢②
矢の種類:中差(戦闘用の矢)
標的:舞を舞っている平家の男
結果:男の頸を射った
結果②:男は舟底へ逆さまに倒れた(射殺されてしまったということ)
「平家の方には音もせず」とは
与一が男の頸を射ると、平家の方はみんな静まりかえってしまったんだね。
与一の腕前をたたえるために舞を舞っていただけなのに、まさか射殺されるとは思ってもみなかったからだね。
ちなみに、ここで登場する「伊勢三郎義盛」とは、源義経の従者で、「義経四天王」の一人だよ。
「扇の的」の中では、那須与一に「義経の命令だ」といって平家の男を射させたね。
「扇の的(平家物語)」表現技法・係り結び
「扇の的」で使われている表現技法や係り結び、古文の文法のポイントなどをまとめたよ。
「扇の的」の表現技法
表現技法とは、文章にリズム感を持たせたり、読む人の印象に残るようなことばを使ったりする表現の工夫こと。
擬音語と擬態語
擬音語とは、「音」をあらわす言葉のうち、自然界の音を表現しているもののこと。
「扇の的」では、与一が矢を射るときや、矢が当たったりするときに擬音語が使われているよ。
擬態語とは、何かの動きや様子を表現するための言葉のこと。
笑っている様子を「にこにこ」とか、くっついている様子を「ベタベタ」とかあらわすよね。
「扇の的」の擬音語
- かぶら矢を放つとき…ひやう(ひょう)
- 扇をいきったとき…ひいふつ(ひいふっ)
- 男の頸を射ったとき…ひやうふつ(ひょうふっ)
「扇の的」の擬態語
- かぶら矢が海へ落ちたときの様子…さつ(さっ)
対句
対句法とは、似たような表現で、同じ内容や対立する内容を並べことでリズムを良くしたり、印象に残るようにする表現技法のひとつ。
「扇の的」では、対句法が使われている部分がいくつかあるよ。
テストでは、「どの部分とどの部分が対句になっているか?」というように問題が出るので、確認しておこう。
「扇の的」の対句の箇所
| 対句➀ | 沖には平家、舟を一面に並べて見物す。 陸には源氏、くつばみを並べてこれを見る。 |
| 対句➁ | かぶらは海へ入りければ、 扇は空へぞ上がりける。 |
| 対句③ | 沖には平家、ふなばたをたたいて感じたり、 陸には源氏、えびらをたたいてどよめきけり。 |
| 対句④ | 平家の方には音もせず、 源氏の方にはまたえびらをたたいてどよめきけり。 |
係り結び
係り結びとは、文の中に「や」「か」「ぞ」「なむ」「こそ」などの係助詞がある場合に、それに対応して文末(結び)の活用語が「連体形」または「已然形」になる法則のこと。
係り結びを使うことで、その文や言葉を強めたり、疑問や反語の意味を持たせることができるんだ。
係り結びの法則(ルール)
係り結びの法則は次の3通り。
- 「や」「か」は疑問または反語の意味を持たせる係助詞で、文末は連体形で結ぶ。
- 「ぞ」「なむ」は強める効果をもつ係助詞で、文末は連体形で結ぶ。
- 「こそ」は強める効果をもつ係助詞で、文末は已然形で結ぶ。
たとえば、「いづれも晴れならずといふことぞなき」は、➁のパターンだね。
係助詞「ぞ」に対応して、「なし」が連体形の「なき」になっているんだ。
「扇の的」で登場する係り結び
| 本文 | 係助詞 | 文末の結び | 意味 |
|---|---|---|---|
| いづれも晴れならずといふことぞなき | ぞ | なし→なき | 強意 |
| 扇も射よげにぞなつたりける | ぞ | けり→ける | 強意 |
| ひいふつとぞ射切つたる | ぞ | けり→ける | 強意 |
| 扇は空へぞ上がりける | ぞ | けり→ける | 強意 |
| 海へさつとぞ散つたりける | ぞ | けり→ける | 強意 |
| 感に堪へざるにやとおぼしくて、 | や | 結びの流れ※ | 疑問 |
※「感に堪へざるにや(あらん)とおぼしくて」は、係助詞の「や」があるけれど、「結び」がなくなってしまっているパターンだよ。
このようなものを「結びの流れ」というんだ。
訳は、「感に堪えないのであろうかと思われて」となって、「疑問」の意味をもつ係り結びだね。
ちなみに、「御定ぞ、つかまつれ。」の「御定ぞ」の「ぞ」は念を押す終助詞で係り結びではないので注意しよう。
打ち消しの「ず」について
「平家の方には音もせず」のように、「〜ず」は打ち消しの助動詞で、否定の意味を持っているよ。
「扇の的(平家物語)」まとめ
- 酉の刻とは、午後六時ごろのこと。
- 擬音語
・かぶら矢を放つとき…ひやう(ひょう)
・扇をいきったとき…ひいふつ(ひいふっ)
・男の頸を射ったとき…ひやうふつ(ひょうふっ) - 擬態語
・かぶら矢が海へ落ちたときの様子…さつ(さっ) - 対句の箇所
➀沖には平家、舟を一面に並べて見物す。
陸には源氏、くつばみを並べてこれを見る。
➁かぶらは海へ入りければ、
扇は空へぞ上がりける。
③沖には平家、ふなばたをたたいて感じたり、
陸には源氏、えびらをたたいてどよめきけり。
④平家の方には音もせず、
源氏の方にはまたえびらをたたいてどよめきけり。 - 係り結びの箇所
➀いづれも晴れならずといふことぞなき
➁扇も射よげにぞなつたりける
③ひいふつとぞ射切つたる
④扇は空へぞ上がりける
⑤海へさつとぞ散つたりける
⑥感に堪へざるにやとおぼしくて、(結びの流れ)
➀~⑤は強意、⑥は疑問
ここまで学習できたら、「扇の的」テスト対策練習問題のページもあるので、ぜひチャレンジしてみてね!
運営者情報

ゆみねこ
詳しいプロフィールを見る
青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-
面白かった
-
分かりやすく、テストの対策として良かった
-
ものすごくわかりやすかった
ありがとうございます!!☺️ -
めちゃくちゃわかりやすかったです!!学校で習ったものの中でも、ノートに書ききれなかったものたかもあったので、、、ありがとうございます✨
ほんとに、どすこいっって感じです((((((((??? -
助かります
-
助かります
-
サイコーだと思ぃ好き
-
これでいい点取れそうです
-
学校の授業でわからないことがあって調べたのですが、とてもわかりやすかったです!
-
いいと思う!
-
おもろ
-
ちょうどいま授業でやっているので、わかりやすかった。
-
わかりやすくて、ほんとに毎回助かっています!
ありがとうございます!!

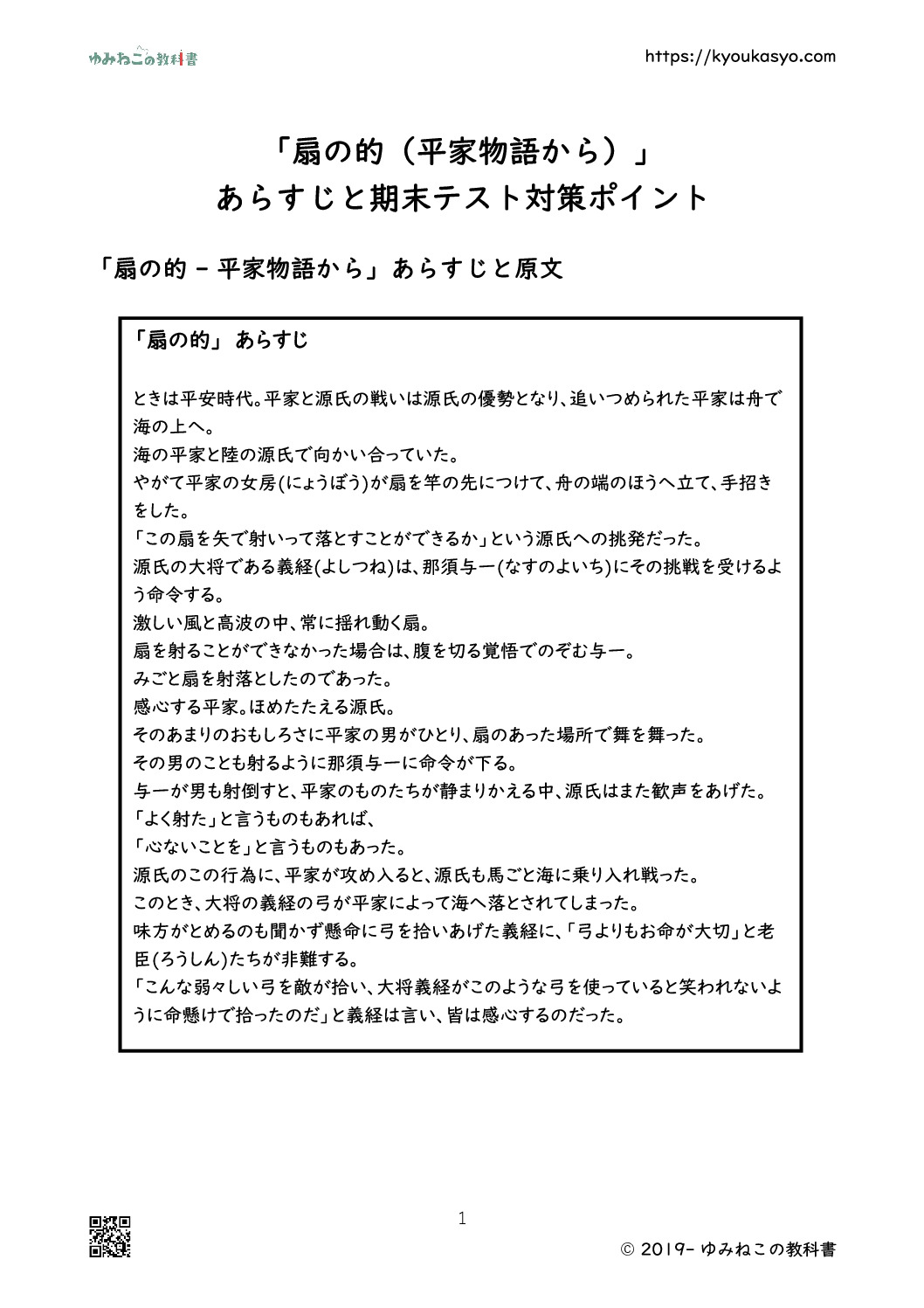

ものすごくわかりやすかった