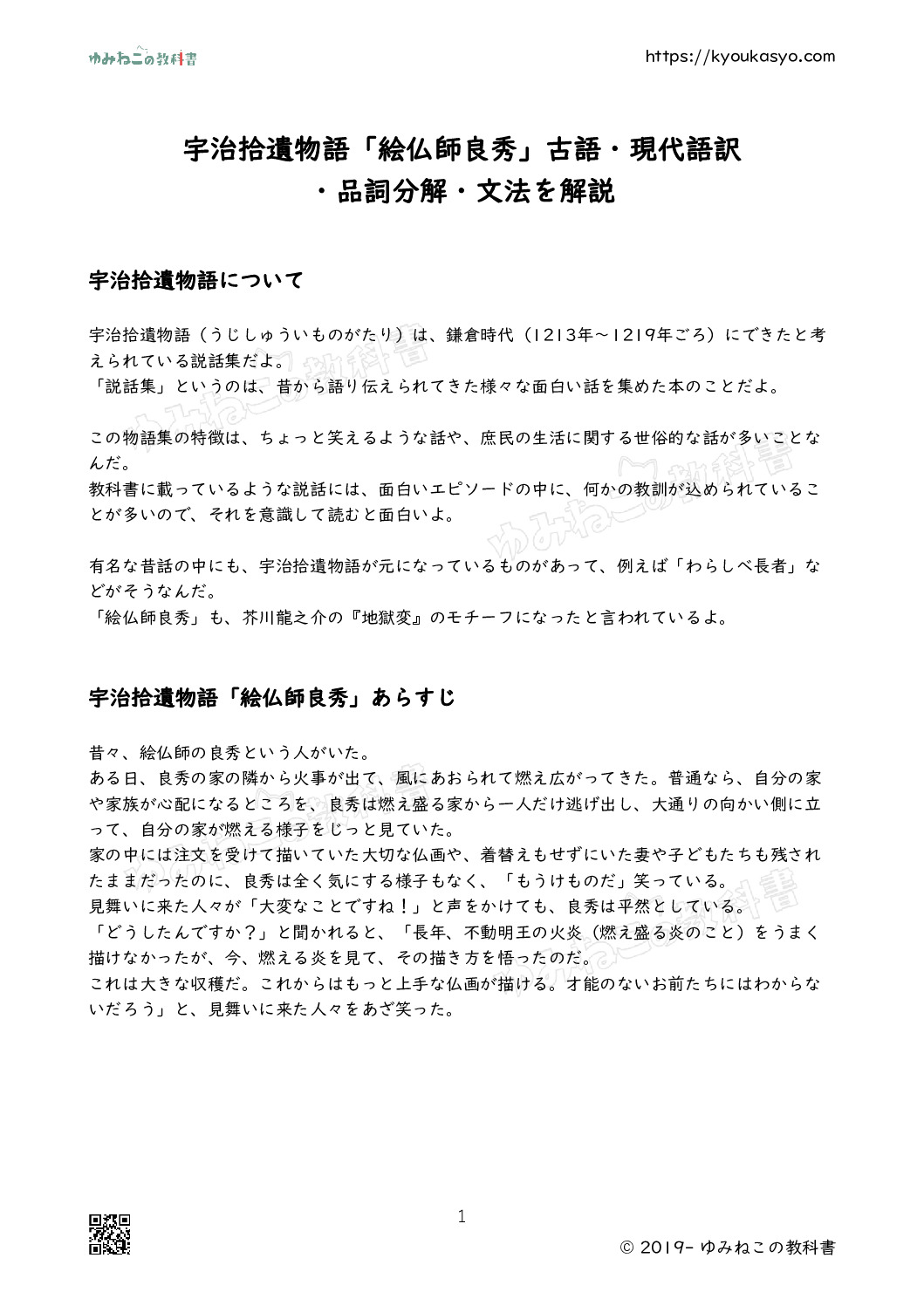宇治拾遺物語「絵仏師良秀」古語・現代語訳・品詞分解・文法を解説
高校古典で学習する宇治拾遺物語の「絵仏師良秀」について、話のあらすじや内容、古語の意味、原文と現代語訳、品詞分解、そして使われている文法のポイントをわかりやすく解説。テストに必要な知識が学べるよ。
宇治拾遺物語について
宇治拾遺物語(うじしゅういものがたり)は、鎌倉時代(1213年~1219年ごろ)にできたと考えられている説話集。
「説話集」というのは、昔から語り伝えられてきた様々な面白い話を集めた本のことだよ。
この物語集の特徴は、ちょっと笑えるような話や、庶民の生活に関する世俗的な話が多いことなんだ。教科書に載っているような説話には、面白いエピソードの中に、何かの教訓が込められていることが多いので、それを意識して読むと面白いよ。
有名な昔話の中にも、宇治拾遺物語が元になっているものがあって、例えば「わらしべ長者」などがそうなんだ。
「絵仏師良秀」も、芥川龍之介の『地獄変』のモチーフになったと言われているよ。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」あらすじ
昔々、絵仏師の良秀という人がいた。
ある日、良秀の家の隣から火事が出て、風にあおられて燃え広がってきた。普通なら、自分の家や家族が心配になるところを、良秀は燃え盛る家から一人だけ逃げ出し、大通りの向かい側に立って、自分の家が燃える様子をじっと見ていた。
家の中には注文を受けて描いていた大切な仏画や、着替えもせずにいた妻や子どもたちも残されたままだったのに、良秀は全く気にする様子もなく、「もうけものだ」笑っている。
見舞いに来た人々が「大変なことですね!」と声をかけても、良秀は平然としている。
「どうしたんですか?」と聞かれると、「長年、不動明王の火炎(燃え盛る炎のこと)をうまく描けなかったが、今、燃える炎を見て、その描き方を悟ったのだ。これは大きな収穫だ。これからはもっと上手な仏画が描ける。才能のないお前たちにはわからないだろう」と、見舞いに来た人々をあざ笑った。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」原文
これも今は昔、絵仏師(えぶつし)良秀(りやうしう)といふありけり。
家の隣より火出(い)で来きて、風おしおほひてせめければ、逃げ出でて、大路(おほち)へ出でにけり。
人の書かする仏もおはしけり。
また衣(きぬ)着ぬ妻子(めこ)なども、さながら内(うち)にありけり。
それも知らず、ただ逃げ出でたるをことにして、向ひのつらに立てり。
見れば、すでにわが家に移りて、煙(けぶり)、炎、くゆりけるまで、おほかた、向かひのつらに立ちて眺めければ、「あさましきこと。」とて、人ども来とぶらひけれど、騒がず。
「いかに。」と人言ひければ、向かひに立ちて、家の焼くるを見て、うちうなづきて、時々笑ひけり。
「あはれ、しつるせうとくかな。年ごろはわろく書きけるものかな。」と言ふ時に、とぶらひに来たる者ども、「こはいかに、かくては立ち給へるぞ。あさましきことかな。物のつき給へるか。」と言ひければ、「なんでふ、物の憑くべきぞ。年ごろ、不動尊の火炎を悪(あ)しく書きけるなり。今見れば、かうこそ燃えけれと、心得つるなり。これこそ、せうとくよ。この道を立てて世にあらむには、仏だによく書き奉(たてまつ)らば、百千(ひやくせん)の家も出で来なむ。わ党(たう)たちこそ、させる能(のう)もおはせねば、物をも惜しみ給まへ。」と言ひて、あざ笑ひてこそ立てりけれ。
その後(のち)にや、良秀がよぢり不動とて、今に人々愛(め)で合へり。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」現代語訳
これも今はもう昔のことだが、絵仏師(仏像や仏画を専門に描く絵師)の良秀という者がいた。
(良秀の)隣の家で火事が起こり、風が覆いかぶさるように(吹き、火が)迫って来たので、(良秀は家から)逃げ出し、大通りへ出た。
(家の中には)人が(良秀に)描かせている仏(の絵)もいらっしゃった。 また、衣服を着ない(良秀の)妻や子なども、そのまま(家の)中にいた。
それも気にせずに、ただ(自分だけが)逃げ出したのを幸いなこととして、(道の)向かい側に立っていた。見ると、(火は)自分(良秀)の家に移っていて、煙や炎が立ちのぼるまで、だいたい(その様子を家の)向かい側に立って(良秀が)眺めていたので、「おどろくほどひどいことだ」と言って人々が見舞いに来たが、(良秀は)動揺する様子がない。 「(動揺しないのは)どうしてか」とある人が言ったところ、(良秀は家の)向かいに立って、(良秀の)家が焼ける様子を見て、うなずいて時々笑った。 「あぁ、大変得をしたものだなぁ。長年、自分は(火炎を)下手に描いてきたものだなぁ。」と(良秀が)言う時に、見舞いに来ている人々が、「これはまたどうして、このように(あなたは)お立ちになっているのか。あきれることだなぁ。物の怪がとり憑いていらっしゃるのか。」と言ったところ、「どうして私に物の怪がとり憑くはずがあろうか(いや、とり憑くはずがない)。長年(私は)不動明王の火炎を下手に描いていたのだ。今見ると、(火炎というものは)このように燃えるものだったのだなあ、と理解したのだ。これこそもうけものだな。この(仏像・仏画を描くという仏絵師の)道を専門としてこの世間に生きるならば、せめて仏だけでも上手に描き申し上げたならば、百(軒)や千(軒)の家もきっと出てくるだろう。お前さんたちこそ、たいした才能もおありでないから、物を惜しみなさるのだ。」と言って、あざ笑って立っていた。
その後であったろうか、良秀が(描いた不動明王は)よじり不動と呼ばれて、今でも人々が称賛し合っている。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」口語訳
これも昔のことなのだけれど、仏像や仏画を専門に描く絵仏師の良秀という人がいたんだ 。
良秀の隣の家で火事が起きて、風がすごくて良秀の家まで火がどんどん迫ってきたから、良秀は慌てて逃げ出して大通りに出たんだ。その時良秀の家には、人に頼まれて描いていた仏様の絵や、着物もきていない奥さんや子どもも、みんなそのまま家の中にいた。なのに良秀は、そんなこと気にしないで、自分が逃げられたことをラッキーだとばかりに大通りの向かい側に立っていた。見たらもう、火は自分の家に燃え移っていて、煙や炎が立ち上るまで、ずっと向かい側から見ていたんだ。
「おどろくほど大変なことですねぇ」と近所の人が見舞いに来たけれど、良秀は全くあわてていない。「どうして冷静なんですか?」と誰かが聞くと、良秀は、向かいに立って、家が燃えるのを見て、うなずいたり、時々笑ったりしていた 。 「ああ、めちゃくちゃ得しちゃったなぁ。おれは長い間、炎の絵をヘタクソに描いてたんだよなぁ」と良秀が言った時、見舞いに来た人たちは、「ちょっと、何でそんなところに立ってるの?ありえないんだけど。まさか、物の怪にでも取り憑かれちゃったの?」と言ったんだ。そしたら良秀は、「なんで物の怪に取り憑かれる必要があるんだよ。長い間、不動明王の炎を下手くそに描いてたんだ。今、炎が燃えているのを見て、炎というものはこうやって燃えるんだってわかったんだよ。これこそ大もうけさ!絵描きの道で生きていくなら、せめて仏様の絵だけでも上手く描けば、家なんて百軒でも千軒でも建つだろうしね。お前たちこそ、たいした才能もないくせに、物を惜しむんだな!」と言って、バカにしたように笑って立っていたんだ。
その後、良秀が描いた不動明王の絵は「良秀のよじり不動」と言われて、今でもみんなが褒め合っているとのことだよ。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」歴史的仮名遣い
絵仏師良秀で使われている歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直したものをまとめているよ。
テストにも出ることがあるので、確認しておこう。
| 歴史的仮名遣い | 現代仮名遣い |
|---|---|
| えぶつし | えぶっし |
| りやうしう | りょうしゅう |
| おしおほひて | おしおおいて |
| おほち | おおち |
| おはしけり | おわしけり |
| 向かひのつら | 向かいのつら |
| おほかた | おおかた |
| とぶらひけれど | とぶらいけれど |
| せうとく | しょうとく |
| なんでふ | なんじょう |
| かうこそ | こうこそ |
| 来なむ | 来なん |
| よぢり不動 | よじり不動 |
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」係り結び
「絵仏師良秀」の中で使われている係り結びについて、使われている部分と係助詞・結び、係り結びの意味をまとめているよ。
| 本文 | 係助詞 | 結び | 意味 |
|---|---|---|---|
| かうこそ燃えけれ | こそ | けれ(已然形) | 強調 |
| あざ笑ひてこそ立てりけれ | こそ | けれ(已然形) | 強調 |
| わ党たちこそ、~物をも惜しみ給へ | こそ | 給へ(已然形) | 強調 |
「わ党たちこそ、させる能もおはせねば、物をも惜しみ給まへ。」の係り結びについて
一般的な解釈では、ここは「こそ」という係助詞を用いた強調構文で、文末の動詞が已然形(=「給まへ」)になっていると考えられるよ。この考え方の「係り結びの仕組み」は以下のとおりになっているんだ。
- 係助詞「こそ」が使われると、文末の述語は已然形になる。
- 「わ党たちこそ」が主語に強調を与え、「させる能もおはせねば」は挿入句となって条件説明をしている。
- 文の結びは「物をも惜しみ給まへ」となり、「給まへ」は尊敬語「給ふ」の已然形。
「こそ」によって、「あなた方こそ(強調)、能力がないから物惜しみをなさるのだ」という皮肉な意味合いとなり、強調された主語が結びの已然形に呼応している、ということだね。
けれど、ここは係り結びが文中で完結しているという解釈も存在すので紹介するね。
「こそ」に呼応する已然形「ね」(助動詞「ず」)が文中で現れていて、その後は命令形で別の文が続いていると考えることができるんだ。
この現象は「結びの流れ」「結びの消滅」と呼ばれていて、係助詞の効力が文中ですでに完了する特殊な用法だよ。
この解釈の場合、「給へ」は已然形ではなく命令形だと考えて、文の意味も「あなた方は、たいした才能もおありにならないからこそ、せめて物だけでも大切になさいませ。」というようにとらえるよ。
文法的にはこのような解釈も可能だけれど、やはりここは文脈的に(良秀が皮肉を込めて「大した才能もないから物を惜しむのだ」と言っていることを考えると、係り助詞「こそ」の結びは「給へ」だというのが一般的な解釈だよ。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」使われている敬語
「絵仏師良秀」の中で使われている敬語について、使われている部分と、どの敬語が使われているのか、誰から誰への敬意なのかをまとめているよ。
| 本文 | 敬語 | 対象 |
|---|---|---|
| 人の書かする仏もおはしけり | 「あり」の尊敬語「おはす」 | 絵の中の仏に対する敬意 |
| かくては立ち給へるぞ | 尊敬の補助動詞「たまふ」 | 見舞いに来た人々から良秀に対する敬意 |
| 物のつき給へるか | 尊敬の補助動詞「たまふ」 | 見舞いに来た人々から良秀に対する敬意 |
| 仏だによく書き奉らば | 「与ふ」の謙譲語「たてまつる」 | 良秀から仏に対する敬意 |
| させる能もおはせねば | 「あり」の尊敬語「おはす」 | 良秀から見舞いに来た人々への敬意 |
| 物をも惜しみ給へ | 尊敬の補助動詞「たまふ」 | 良秀から見舞いに来た人々への敬意 |
ただし、ここで良秀から見舞いに来た人々へ対して使われている敬語には、単なる「敬意」を示すためではないよ。
なぜなら、良秀は、見舞いに来た人々をあざ笑っているよね。
ここでの敬語は、「皮肉」や「ばかにしている」ニュアンスを強めるために、わざと敬語が使われていると考えることもできるよ。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」話の内容とポイント
「それも知らず、ただ逃げ出たるをことにして」の「それ」とは
「それも知らず、ただ逃げ出たるをことにして」の「それ」は、絵仏師良秀が火事の中、家に残してきたものを指しているよ。
具体的には、つぎの2つが原文に書かれているね。
- 人の描かする仏(仏画):他人が注文して良秀に描かせていた仏の絵のこと
- 衣着ぬ妻子(妻や子ども):着物を着ていない良秀の妻や子
良秀は、自分が描いていた仏の絵や、妻と子供がまだ家の中に残っているのに、それを気にせず、ただ自分が逃げ出したことを「ラッキー」と思って、大通りの向かい側に立って火事の様子を見ていたというこどだね。
自己中心的で、自分の芸術への執着が家族よりも優先される人物像が伝わるね。
なぜ妻子は着物を着ていなかったの?
絵仏師良秀の舞台は、平安時代と考えられているよ。
この時代の庶民は布団を持っていなくて、昼間に自分たちが着ていた着物を布団替わりに体にかけて寝ていたんだ。
火事が起きたのが夜だったので、寝ていた妻子は着物を着ていなかったのだと考えることができるよ。
「人の書かする仏」とは
「人の書かする仏」とは、他人が良秀に注文して描かせている仏の絵(仏画)のこと。
「人の」の「の」は、主格の「の」で、「人が」と訳すよ。
「書かする」の「する」は使役の助動詞で、「~させる」という意味になるんだ。なので、「書かする」は「(人に)描かせる」ということになるよ。
「人の書かする仏もおはしけり」の「おはしけり」は、「あり」の尊敬語の「おはす」の連用形に、過去の助動詞「けり」の終止形が接続しているよ。
「おはす」が「いらっしゃる」になるので、過去の助動詞がついて「いらっしゃった」となるね。
良秀が描いたものとはいえ、仏様の絵なので、尊敬語を使って敬意を表しているんだね。
何を「わろく書きける」なのか
「わろく」とは、「下手に」という意味。
「年ごろ」とは、「長年」ということ。
なにを長年下手に描いていたのかというと、「不動尊の火炎(不動明王の背中の火炎)」のことだね。
不動明王とは
不動明王は、日本で一番信仰されている仏さまのひとり。
「不動」とは「動かない」という意味で、これは人々を救うまで動かない、揺るぎない強い決意を持っていることを表しているよ。
人々の心の中の悪や悪魔を追い払うために、おそろしい顔をしているんだ。
背中の火炎は、不動明王の身体から出ている光を表していて、煩悩を焼き尽くすほどの燃えさかる炎を表しているよ。
原文では、「わろく書きける」のほかに、「悪しく書きける」という表現もでてくるよね。
「わろし」と「悪し」はどちらも「良くない・悪い」という意味なんだけれど、違いがあるんだ。
「わろし」と「悪し」の違いについて
「わろし」:他と比べて悪い様子
「悪し」:絶対的に(他と比べなくても)悪い様子
良秀は、火事で実際の炎が燃えるようすをみて、本物の炎に比べて、自分が長年描いてきた火炎が「劣っている」と思ったんだね。
「この道」とは何のことか
「この道」とは、良秀が絵仏師として生きる道、つまり「仏画を描くこと」を指しているよ。
良秀は仏の姿を描く専門の絵師なので、素晴らしい仏画が描けるかどうかが生活に直結するんだ。
仏画の依頼が入らなければ、暮らしに困ってしまうからね。
逆に、上手に仏画が描けるようになれば、家が百軒でも千軒でも建てられるくらい、お金に困らなくなるということだね。
火事が起きて、燃えさかる炎を実際に目にしたことで、これまでずっと上手く描けなかった不動明王の火炎を、どう描けば良いのかが理解できたんだ。
良秀にとって、「この道」とは、生活費を稼ぐ方法であると同時に、自分自身の芸術を追求する道でもあるよ。
その道を進む良秀には、火事さえも、仏絵師としての自分の技術を高めるための貴重な経験だったと受け取っているんだね。
テストでも「この道」とは何か?という問題はよく出るので、しっかりおさえよう。
「これこそ、せうとくよ」の「これ」とは
「これこそ、せうとくよ」の「これ」とは、良秀が自分の家が燃えてしまうときの実際の炎を見て、長年自分が下手に描いてきた不動明王の背中の火炎をどう描けばよいのかを理解できたことを指しているよ。
「年ごろはわろく書きける」とあるように、実際の炎の燃え方を見た良秀は、自分が長年描いてきた炎が「本当の炎よりも劣っている」ことに気がついたんだよね。
もし実際の炎を見ないままだったら、自分の描く炎が下手だったことにも気がつかないままだったかもしれない。
絵仏師として、不動明王の背中の火炎の描き方を向上させることができる重要なきっかけとなったことを「これこそ、せうとくよ」と表現しているんだね。
良秀が「これこそ、せうとくよ。」と言った理由
「せうとく」は、「もうけ物」という意味。
なので、「これこそ、せうとくよ」は、「これこそもうけ物よ」。という意味になるね。
「これ」とは、火事の炎を実際に見たことで、自分の描いてきた不動明王の火炎が下手だったということを理解したことだったね。
ではなぜそれが「もうけ物」なのかというと、絵仏師にとって、仏画を上手く描けるかどうかは死活問題だよね。
上手く描ければ、それだけたくさんの注文が入るから、お金に困らなくなるよね。
実際の炎を目にして、「炎とは、このように燃えるのか。」と理解できた良秀は、これからは今までよりも上手に不動明王の火炎を描けると思ったんだね。
だから、「これこそ、せうとくよ。」と言ったんだね。
「いかに。」の意味
見舞いに来た人々は、良秀の様子を見て「いかに。」と言ったね。
「いかに。」という言葉は、副詞で、「どうして」という意味なんだ。
普通、火事が起きて、妻子もまだ家に取り残されている状況だったら、慌てふためくはずだよね。
それなのに、まったく慌てる様子もなく、自分の家が燃えているのを立って見ているだけの良秀の様子に疑問を抱いて、「いかに。」と言ったんだね。
「こはいかに、」に込められた気持ち
慌てずにただ立って家が燃えているのを見ているだけの良秀の様子に、人々は「いかに。」と言っていたのだけれど、さらに良秀は、見ているだけどころか時々うなずいて笑っていたりまでしたんだよね。
ただ見ているだけなら、まだ「ショックのあまり動けないのかな」とも思えるけれど、うなずいて笑っているなんて、とても正気だとは思えないよね。
だから、人々は「こはいかに、」とさらに「強い驚き」と「あきれ」の気持ちを込めて言ったんだね。
「物のつき給へるか。」と人々が言った理由
火事で家が燃えて、その中に妻子が取り残されているというとんでもなくひどい状況の中で、うなずいて笑ってさえいる良秀の様子に、見舞いに来た人々は「とても正気だとは思えない=物の怪が取りついているのでは」と思ったんだね。
「この道を立てて」とは
「この道を立てて」とは、良秀が仏画を描く道を職業として選び、その道で身を立てていくという意味だよ。
「立て」は、「立つ」という動詞の連用形で、「~を専門とする」という意味を持っているんだ。
単に仏画を描いていく、というだけではなくて、それを専門にして生活費を稼ぎ、自分自身の人生をその道に捧げるという強い意志が感じられる言葉だね。
良秀が自分の家が焼けるのを見て喜んだのは?
良秀は、火事で自分の家が焼けてしまっているのに、その様子を見て頷いたり、笑ったりしていたね。
本来だったら、自分の家が焼けてしまっている状況で笑うことなんてできないはずだね。
そんな状況にもかかわらず、良秀が自分の家が焼けるのを見て喜んでいたのは、今回の火事が、自分の芸術を大きく進歩させるきっかけになったと考えたからだね。
具体的にいうと、これまでは不動明王の炎をうまく描けなかったのが、火事で本物の炎を見て、「炎とはこうやって萌えるんだ!」とリアルな炎の描き方を理解できたことで、これからの自分の絵仏師としての技術が向上したと思ったんだね。
良秀にとっては、家族や家よりも、自分の芸術のほうが大切だったことがわかるね。
良秀はなぜ人々をあざ笑ったのか?
火事で見舞いに来た人々は、「大変なことですね」と心配したり、火事を見て笑っている良秀の様子を「もののけに取り憑かれたのか」と不思議がったりしていたよね。
良秀が、そんな人々のことをあざ笑ったのは、この火事によって良秀が得た絵仏師としての技術の価値を理解してない人々を、「才能がないからわからないんだ」と見下したから。
火事によって家や家族を失ったことはたしかに大変なことだけれど、良秀にとってはそれよりも、長年の課題だった「炎の描き方をマスターできた」ということの方が重要で、大きな収穫とさえ感じていたんだ。
それなのに、それもわからずに家や家族を惜しむ人々のことを、これといった才能がないから、そんなものを惜しむのだ、と馬鹿にしたんだね。
良秀の人物像
家が火事になって、仏画や妻子がまだ家の中に取り残されているのにもかかわらず、気にもせずに自分だけ逃げ出して通りの向かい側から燃える家を眺めている様子からは、良秀の自己中心的で一般常識からはかなりズレていることが伝わるね。
家や妻子を失ってしまったことよりも、リアルな炎の描き方が分かったことのほうが「もうけものだ」と感じていることからは、「自分の芸術」が絶対であるという価値観が読み取れるよ。
見舞いに来た人々を逆にあざ笑う態度からは、やはり自己中心的で、傲慢な一面も見えるね。
一言で言うと、「芸術絶対主義!」でかなり変わった価値観とモラル感を持つサイコパスという感じ…?
でもその一方で、良秀の芸術に対するまっすぐな思いはレベル違いということもわかるね。
これほどまでに自分の芸術を極めることを一番とした良秀だからこそ、彼の作品「よぢり不動」は人々の心をとらえ、称賛されたんだね。
絵仏師良秀は実在の人物か?
宇治拾遺物語は「説話集」だね。
説話とは、語り継がれた伝説や神話などのことなんだ。
なので、完全にフィクションというよりは、モデルになった事件や人物がいた可能性が高いと考えることもできるよ。
ということは、絵仏師良秀も、モデルとなった人や事件が実際にあったのかもしれないね。
一説には、平安時代後期にいた絵仏師がモデルになったと言われているよ。
「よぢり(よじり)不動」とは
「よじる」とは、「ねじる」こと。
「よじり不動」は、背中の炎のあまりの熱さに、不動明王が思わず身体をよじって(ねじって)しまっている様子を表しているんだ。
つまり、不動明王本人さえも身をよじるほど、背中の炎が燃えさかっていることを表現しているんだね。
実際の火事を目の当たりにした良秀だからこそ描けた作品ということで、人々の称賛を得ているのかもしれないね。
宇治拾遺物語の「絵仏師良秀」は、常識では考えられないような行動をとる良秀を通して、芸術に対する強烈な執念を描いた作品と言えるよ。
良秀のとった行動は倫理的には問題があるかもしれないけれど、その狂気とも言える情熱が、後世にまで残る素晴らしい作品を生み出したことも事実だよね。
この物語から何を学ぶかは、読む人それぞれなんだ。
良秀の生き方を「おかしい」「ひどい」と感じる人もいると思うけれど、良秀の徹底したプロ意識や、目標のためには手段を選ばない姿勢に、何か心を揺さぶられるものがあるかもしれないね。
実際、芥川龍之介の『地獄変』という小説はこの「絵仏師良秀」がモチーフになっていると言われているし、三島由紀夫がそれを基に歌舞伎や映画を制作したりしたことからもわかるように、良秀の強烈な生き方は後世の人々に何らかの衝撃や影響を与えたと考えられるよ。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」古語の意味
「絵仏師良秀」の中で使われている意味を紹介しているよ。
| 古語 | 意味 |
|---|---|
| 絵仏師 | 仏教絵画を専門とする画家のこと。 |
| 良秀 | 平安時代後期の絵仏師。実際に存在した人物かどうかは不明。 |
| おしおふ | 押し覆ふ。 おおいかぶせること。 |
| せむ | 迫む。 差し迫ること。 |
| 大路 | 大通り |
| 書かする | 「書く」の未然形+使役の助動詞「す」の連体形 書かせる。 |
| おはす | 「あり」の尊敬語 いらっしゃる・おありになる |
| 妻子 | 妻と子供 |
| さながら | 然ながら そのまま。もとのまま。 |
| ことにして | よいことにして。 |
| 向かひのつら | 道の向かい側。 |
| くゆりける | 煙やにおいが立ち上るという意味の「くゆる」の連用形「くゆり」+過去の助動詞「けり」の連体形 |
| おほかた | 全体・だいたい |
| あさましき | 驚くほど大変だ・ひどい |
| とぶらふ | 訪問する・見舞う |
| いかに | なぜ |
| うちうなづく | 軽くうなずく |
| あはれ | 感動を表す感動詞で、「ああ、すばらしい」「ああ、たいへんな」といった感慨を表す。 |
| しつる | サ行変格活用動詞「す」の連用形「し」に、完了の助動詞「つ」の連体形「つる」が接続した形。 主な意味は、「~し終えた」だが、この文での「しつる」は、良秀の強い達成感や肯定的な満足を含む「うまくやった」というニュアンスになる。 |
| せうとく | 「所得」と書く。 得をすること・もうけ物。 現代仮名遣いでは「しょうとく」 |
| 年ごろ | 長年の間 |
| わろく | みっともない・下手だ |
| 書く | ここでは仏の姿を描くこと |
| かくては | このままでは |
| 物のつく | ここでは「物の怪がとり憑く」 |
| なんでふ | 反語の表現。 「どうして~か。いや、~ない」という意味。 「なにといふ」が変化している。 |
| 悪し(あし) | 良くない |
| かうこそ | まさにこのように |
| 心得(こころえ)つる | 「心得(こころう)」の連用形のため「こころえ」となっている。 「つる」は完了の助動詞の連体形。 理解する。 |
| 世にあらむ | 世間にみとめられている |
| だに | 副助詞 「せめて~だけでも」 |
| わ党 | あなたたち・おまえたち |
| させる | 連体詞 多くは下に打ち消しの語を伴う。 これというほどの・それほどの・たいした。 |
| 能 | 才能・能力 |
| あざ笑ふ | 相手を見下して、馬鹿にするように笑うこと |
| めで合へり | 「めづ」+「合ふ」の複合動詞「めで合ふ」の已然形に、存続の助動詞「り」が接続している。 「(共感して)称賛し合っている」という意味。 |
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」文法のポイント
「これも今は昔、絵仏師良秀といふありけり」の「いふ」の後の省略について
「これも今は昔、絵仏師良秀といふありけり」の「いふ」の後の省略について、文法的に説明するよ。
「いふ」はハ行四段活用動詞「いふ」(言う)の連体形。
古文において、連体形は体言(名詞)を修飾する役割を持つんだけれど、この文脈では、連体形の後によくある体言、特に「者(もの)」が省略されていると解釈するんだ。
具体的には、この句は直訳すると「これも今は昔、絵仏師良秀と言う~がいた」となって、省略された「もの」を補うことで「これも今は昔、絵仏師良秀という者がいた」という意味になるんだよ。
文法的なポイント
- 【連体形(連体修飾形)の用法】
動詞や形容詞、助動詞の連体形は、名詞(体言)を修飾する。 - 【体言の省略】
古文では、文脈から明らかな場合や、特定の慣用的な表現において、体言が省略されることがある。 - 【「いふ」の連体形と「者」の省略】
「~といふ者」は、「~という名前の者」「~という職業の者」「~というような者」といった意味で、人物や物事を説明する際によく用いられる定型的な表現。この「者」は、多くの場合、特に人物について述べる際に省略される。
なので、「これも今は昔、絵仏師良秀といふありけり」における「いふ」の後は、人物を表す体言「者(もの)」が省略された連体修飾の形であると文法的に説明できるんだ。
これにより、「絵仏師良秀という人がいた」という自然な意味になるよ。
【超重要】助動詞「り」の特殊な接続ルール:「サ未四已」をマスターしよう!
【重要ポイント:助動詞「り」の特殊な接続ルール】
「立てり」の「り」は、動作が完了したり、状態が続いていたりすること(完了・存続)を表す助動詞なんだ。
この助動詞「り」は、くっつく相手(動詞の活用形)がとても特殊で、テストでも超頻出だから、必ず覚えよう!
接続ルール:「サ未四已(さみしい)」
・サ行変格活用動詞の未然形(例:「せ」)
・四段活用動詞の已然形(例:「立て」)
このルールに当てはめると、「立てり」は、タ行四段活用動詞「立つ」の已然形「立て」に、「り」が接続していることがわかるね。これが、学校のテストで100点を取るための完璧な答えだよ。
【もっと知りたいキミへ:なぜこんな複雑なルールに?】
実は、この「立てり」という言葉は、もともと「立ちてあり」という言葉が、時代と共に発音しやすく変化して生まれたものなんだ。
だから、「立つ」の連用形「立ち」が関係している、という歴史的な背景もあるよ。
でも、古典文法を学ぶ上では、まずは「サ未四已」というルールを完璧にマスターすることが大切だよ!
「せめければ」の接続助詞「ば」の意味の見分け方
接続助詞の「ば」が使われているとき、その文がどんな意味になるかを見分けるコツがあるよ。
それは、「ば」の直前の言葉が、どんな形(活用形)をしているかを見ること。
接続助詞「ば」の使われ方には、つぎの2パターンしかないんだ。
-
- 「ば」のすぐ手前の言葉がまだ起こってないことを表す「未然形」になっている時
-
- 「ば」のすぐ手前の言葉がすでに起こったことや常に起こることを表す「已然形」になってる時
「ば」の直前が未然形の場合は、まだ実現してないことを仮定して言う時に使う仮定条件の意味になるんだ。現代語訳のイメージは、「もし〜ならば」「もし〜たら」となるよ。
「さながら内にありけり」の「あり」
「さながら内にありけり」の「あり」は、ラ行変格活用動詞「あり」の連用形で「いる」という意味だね。
なので、「さながら内にありけり」は、「全てそのまま家の中にいた」という意味になるよ。
古文のラ行変格活用動詞は、「あり」「をり」「はべり」「いまそか(か)り/いますが(か)り」などが重要なのでおさえておこう。
「とぶらひに来たる者ども」の「来」
「とぶらひに来たる者ども」の「来」は、カ行変格活用動詞「来(く)」の連用形。
この文では、「とぶらひに来(き)たる」と続いて、動詞「とぶらふ」(見舞う、安否を問う)に連なって動作を表しているんだ。
なので、「とぶらひに来たる者ども」は、「見舞いに来た人々」という意味になるよ。
「今見れば」の「見れ」
「今見れば」の「見れ」は、マ行上一段活用動詞「見る」の已然形。
ソース の品詞分解では、「見れ」は以下のように解説されています
已然形は、接続助詞「ば」 を伴って、主に以下の意味を表すんだ。
【確定条件・原因理由】
~ので、~から(すでに実現している事柄、または事実として認められる事柄)
【偶然条件】
~ところ、~と(偶然起こった事柄)
【恒常条件・習慣】
~といつも、~するたびに(いつもそうなる事柄、習慣的な事柄)
【余韻・詠嘆】
~だなあ(文末に「め」「も」「かな」などを伴うことが多い)
「今見れば」の場合、「ば」は確定条件を表していて、「今見てみると、~である」というような意味合いになるよ。
ある状況を観察した結果として次の事柄が起こったことを示しているんだね。
マ行上一段活用動詞は、「着る」なども同じ活用をするので、あわせて覚えておこう。
「心得つるなり」の「心得」
「心得つるなり」の「心得」は、ア行下二段活用動詞「心得(こころう)」の連用形で、「理解する」という意味だね。
なので、「心得」は「理解し」という意味を持つよ。
この連用形に、完了の助動詞「つ」の連体形「つる」と、断定の助動詞「なり」の終止形「なり」が続いて、「(~と)理解したのだ」という意味の文語的な表現となっているんだ。
「させる能もおはせねば」の「おはせ」
「させる能もおはせねば」の「おはせ」は、尊敬のサ行変格活用動詞「おはす」の未然形。
「おはす」は「あり」の尊敬語で、「おありになる」という意味を持っていて、ここでは良秀から見舞いに来た人々への敬意を表しているんだ。
「させる能もおはせねば」は、「それほどの才能もおありにならないので」という意味になるよ。
「ねば」は打消の助動詞「ず」の已然形「ね」に接続助詞「ば」が付いたもので、ここでは原因・理由を表しているよ。
完了の助動詞「ぬ」と「つ」の違いについて
古文で出てくる「ぬ」と「つ」は、どちらも完了(動作が完全に終わったこと)や強意(強く言い切る気持ち)を表す助動詞だけれど、それぞれに異なるニュアンスや使われ方の特徴があるんだ。
簡単に言うと、
「ぬ」:自然にそうなった、無意識のうちに完了した
「つ」:意志的に、または急に、完了した
という違いになるよ。
完了の助動詞「ぬ」
「ぬ」は、自然的な完了を表すことが多いよ。
人の意志が関わらない出来事や、自然に進行して完了したこと、無意識のうちにそうなってしまったことなどに使われるんだ。
| ニュアンス | 「~してしまった」「~し終わった」「~した」 まるで、時間とともに自然に終わったような感じ。 |
| 使われる場面 | 自然現象: 「雨が降りぬ」(雨が降ってしまった) 状態の変化: 「花が咲きぬ」(花が咲き終わった) 無意志的な動作: 「忘れぬ」(うっかり忘れてしまった) しばしば「~てしまった」という、少し残念な気持ちや、意図しない完了を表すこともある。 |
| 例文 | 「月、入りぬ。」(月が沈んでしまった。) 月が自然に沈む様子。 「道は遠く成りぬ。」(道が遠くなってしまった。) 自然に遠く感じるようになった様子。 |
完了の助動詞「つ」
「つ」は、意志的な完了や、急に・勢いよく行われた完了を表すことが多いよ。
人の意図が関わる動作や、瞬時に完了したことを強調する際に使われるんだ。
| ニュアンス | 「~してしまった」「~し終えた」「きっぱりと~した」 何かをやり遂げた感じや、素早く終わらせた感じ。 |
| 使われる場面 | 意志的な動作: 「書きつ」(書き終えた)、「食べつ」(食べ終えた) 急な動作: 「飛び立ちつ」(さっと飛び立った) 準備の完了: 「用意しつ」(用意し終えた) 「~てしまう」という、きっぱりと完了した意味や、達成感を伴うこともある。 |
| 例文 | 「弓をとりつ。」(弓を取り、構えた。) 意志的な動作が完了した様子。 「いざ、出で立ちつ。」(さあ、出発しよう。) 素早く、きっぱりと出発する様子。 |
完了の助動詞「ぬ」と「つ」の違い
| 助動詞 | 主なニュアンス | 主な対象 | 例文 |
|---|---|---|---|
| ぬ | 自然に完了、無意志、結果 | 自然現象、状態、無意識の動作 | 「雨が降りぬ」(自然に降った) |
| つ | 意志的完了、急激、達成感 | 人の動作、瞬間的な完了 | 「弓を取りつ」(自分で取った) |
「めで合へり」
「めで合へり」は、以下の要素から構成されているよ
-
- 【めで合へ】ハ行四段活用動詞「愛で合ふ(めであふ)」の已然形
-
- 【り】存続の助動詞「り」終止形
「愛で合ふ」は、動詞「愛でる」と動詞「合ふ」が複合した動詞なんだ。
「愛でる」は、「美しいと思って大切にする」「ほめる」「喜ぶ」といった意味を持ち、「合ふ」は、ここでは「互いに~する」という意味合いを添えていて、相互行為であることを表しているよ。
なので、「愛で合ふ」は、「互いに褒め合う」「共感して賞賛し合う」といった意味になるんだ。
「めで合へ」は、この「愛で合ふ」の已然形で、已然形は後に接続する語によって意味合いが変わるよ。
ここでは存続の助動詞「り」に接続しているね。
存続の助動詞「り」は、動作や状態が持続していること、または動作の結果が残っている状態を表すよ。現代語の「~ている」に近い意味合いだね。
「り」の形は終止形になっているね。
文末にあるため、終止形が用いられているんだ。
なので、「めで合へり」全体としては、「(人々が)互いに褒め称え合っている」「(人々が)共感して賞賛し合っている」という、その状態が続いていることを表すよ。
物語の結びの部分で使うことで、良秀の描いた不動明王がその後も長く人々に称賛されている様子を示しているんだ。
宇治拾遺物語「絵仏師良秀」品詞分解
| これ | 代名詞 |
| も | 係助詞 |
| 今 | 名詞 |
| は | 係助詞 |
| 昔 | 名詞 |
| 絵仏師良秀 | 名詞 |
| と | 格助詞 |
| いふ | 動詞:ハ行四段活用「いふ」の連体形 ※その後に続く「者」などが省略されている。 |
| あり | 動詞:ラ行変格活用「あり」の連用形 |
| けり | 過去の助動詞「けり」の終止形 |
| 家 | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| 隣 | 名詞 |
| より | 格助詞 |
| 火 | 名詞 |
| 出で来 | 動詞:カ行変格活用「出で来」の連用形 |
| て | 接続助詞 |
| 風 | 名詞 |
| おしおほひ | 動詞:ハ行四段活用「おしおほふ」の連用形 |
| て | 接続助詞 |
| せめ | 動詞:マ行下二段活用「せむ」の連用形 |
| けれ | 過去の助動詞「けり」の已然形 |
| ば | 接続助詞 |
| 逃げ出で | 動詞:ダ行下二段活用「逃げ出づ」の連用形 |
| て | 接続助詞 |
| 大路 | 名詞 |
| へ | 格助詞 |
| 出で | 動詞:ダ行下二段活用「出づ」の連用形 |
| に | 完了の助動詞「ぬ」の連用形 |
| けり | 過去の助動詞「けり」終止形 |
| 人 | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| 書か | 動詞:カ行四段活用「書く(描く)」の未然形 |
| する | 使役の助動詞「す」の連体形 |
| 仏 | 名詞 |
| も | 係助詞 |
| おはし | 動詞:サ行変格活用「おはす」の連用形。 ※「おはす」は「あり」の尊敬語 |
| けり | 過去の助動詞「けり」の終止形 |
| また | 接続詞 |
| 衣 | 名詞 |
| 着 | 動詞:カ行上一段活用「着る」の未然形 |
| ぬ | 打消の助動詞「ず」連体形 |
| 妻子 | 名詞 |
| など | 副助詞 |
| も | 係助詞 |
| さながら | 副詞 |
| 内 | 名詞 |
| に | 格助詞 |
| あり | 動詞:ラ行変格活用あり」の連用形 |
| けり | 過去の助動詞「けり」の終止形 |
| それ | 代名詞 |
| も | 係助詞 |
| 知ら | 動詞:ラ行四段活用「知る」の未然形 |
| ず | 打消の助動詞「ず」の連用形 |
| ただ | 副詞 |
| 逃げ出で | 動詞:ダ行下二段活用「逃げ出づ」の連用形 |
| たる | 完了の助動詞「たり」の連体形 |
| を | 格助詞 |
| ことにし | 名詞「事」+格助詞「に」+サ行変格活用の動詞「為(す)」の連用形。 →「ことにす」は、「(それで)よいこととする」という意味。 |
| て | 接続助詞 |
| 向かひ | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| つら | 名詞 |
| に | 格助詞 |
| 立て | 動詞:タ行四段活用「立つ」の已然形 |
| り | 存続の助動詞「り」の終止形 ※助動詞「り」は四段動詞の已然形に接続する「サ未四已」のルールを思い出そう! |
| 見れ | 動詞:マ行上一段活用「見る」の已然形 |
| ば | 接続助詞 |
| すでに | 副詞 |
| わ | 代名詞 ※自分自身を指す言葉 |
| が | 格助詞 |
| 家 | 名詞 |
| に | 格助詞 |
| 移り | 動詞:ラ行四段活用「移る」の連用形 |
| て | 接続助詞 |
| けぶり(炎) | 名詞 |
| くゆり | 動詞:ラ行四段活用「くゆる」の連用形 |
| ける | 過去の助動詞「けり」の連体形 |
| まで | 副助詞 |
| おほかた | 副詞 |
| 向かひ | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| つら | 名詞 |
| に | 格助詞 |
| 立ち | 動詞:タ行四段活用「立つ」の連用形 |
| て | 接続助詞 |
| ながめ | 動詞:マ行下二段活用な「ながむ」の連用形 |
| けれ | 過去の助動詞「けり」の已然形 |
| ば | 接続助詞 |
| あさましき | 形容詞:シク活用「あさまし」の連体形 |
| こと | 名詞 |
| とて | 格助詞 |
| 人ども | 名詞 ※「人」に、言葉の後ろに付いて、その言葉に特定の意味やニュアンスを加えたり、新しい言葉を作ったりする接尾語「ども」がついている。 「ども」は、名詞、特に人や動物を表す言葉に付いて、複数であることを示す。 |
| 来 | 動詞:カ行変格活用「来」の連用形 |
| とぶらひ | 動詞:ハ行四段活用「とぶらふ」の連用形 |
| けれ | 過去の助動詞「けり」の已然形 |
| ど | 接続助詞 ※逆接の接続助詞。 |
| 騒が | 動詞:ガ行四段活用「騒ぐ」の未然形 |
| ず | 打消の助動詞「ず」の終止形 |
| いかに | 副詞 |
| と | 格助詞 |
| 人 | 名詞 |
| 言ひ | 動詞:ハ行四段活用「言ふ」の連用形 |
| けれ | 過去の助動詞「けり」の已然形 |
| ば | 接続助詞 |
| 向かひ | 名詞 |
| に | 格助詞 |
| 立ち | 動詞:タ行四段活用「立つ」の連用形 |
| て | 接続助詞 |
| 家 | 名詞 |
| の | 格助詞 |
| 焼くる | 動詞:カ行下二段活用「焼く」連体形 |
| を | 格助詞 |
| 見 | 動詞:マ行上一段活用「見る」の連用形 |
| て | 接続助詞 |
| うちうなづき | 動詞:カ行四段活用「うちうなづく」の連用形 ※接頭語「うち」+動詞「うなづく」。接頭語「うち」は、動詞の前に付いて、その動作を軽く行うというニュアンスを加える。 |
| て | 接続助詞 |
| ときどき | 副詞 |
| 笑ひ | 動詞:ハ行四段活用「笑ふ」の連用形 |
| けり | 過去の助動詞「けり」の終止形 |
| あはれ | 感動詞 |
| しつる | サ行変格活用動詞「す」の連用形+完了の助動詞「つ」の連体形「つる」 動詞:サ行変格活用「す」の連用形 |
| せうとく | 名詞 |
| かな。 | 終助詞 |
| 年ごろ | ー |
| は | 係助詞 |
| わろく | 形容詞 ク活用「わろし」の連用形 |
| かき | カ行四段活用・連用形 |
| ける | 過去の助動詞・連体形 |
| もの | ー |
| かな。」 | 終助詞 |
| と | 格助詞 |
| 言ふ | ハ行四段活用・連体形 |
| 時 | ー |
| に、 | 格助詞 |
| とぶらひ | ー |
| に | 格助詞 |
| 来 | カ行変格活用・連用形 |
| たる | 完了の助動詞・連体形 |
| 者ども、 | ー |
| 「こ | 代名詞 |
| は | 係助詞 |
| いかに、 | 副詞 |
| かくて | 副詞 |
| は | 係助詞 |
| 立ち | タ行四段活用「立つ」の連用形 |
| たまへ | 尊敬の補助動詞ハ行四段活用「たまふ」の已然形 |
| る | 存続の助動詞「り」の連体形 |
| ぞ。 | 終助詞 |
| あさましき | 形容詞・シク活用・連体形 |
| こと | ー |
| かな。 | 終助詞 |
| もの | ー |
| の | 格助詞 |
| つき | カ行四段活用・連用形 |
| たまへ | 尊敬の補助動詞・ハ行四段活用・命令形 |
| る | 存続の助動詞・連体形 |
| か。」 | 係助詞 |
| と | 格助詞 |
| 言ひ | ハ行四段活用・連用形 |
| けれ | 過去の助動詞・已然形 |
| ば、 | 接続助詞 |
| 「なんでふ | 副詞 |
| もの | ー |
| の | 格助詞 |
| つく | カ行四段活用・終止形 |
| べき | 当然の助動詞・連体形 |
| ぞ。 | 終助詞 |
| 年ごろ | ー |
| 不動尊 | ー |
| の | 格助詞 |
| 火炎 | ー |
| を | 格助詞 |
| あしく | 形容詞・シク活用・連用形 |
| かき | カ行四段活用・連用形 |
| ける | 過去の助動詞・連体形 |
| なり。 | 断定の助動詞・終止形 |
| 今 | ー |
| 見れ | マ行上一段活用・已然形 |
| ば、 | 接続助詞 |
| かう | 副詞 |
| こそ | 係助詞 |
| 燃え | ヤ行下二段活用・連用形 |
| けれ | 詠嘆の助動詞・已然形 |
| と、 | 格助詞 |
| 心得 | ア行下二段活用・連用形 |
| つる | 完了の助動詞・連体形 |
| なり。 | 断定の助動詞・終止形 |
| これ | 代名詞 |
| こそ | 係助詞 |
| せうとく | ー |
| よ。 | 間投助詞 |
| こ | 代名詞 |
| の | 格助詞 |
| 道 | ー |
| を | 格助詞 |
| 立て | タ行下二段活用・連用形 |
| て | 接続助詞 |
| 世 | ー |
| に | 格助詞 |
| あら | ラ行変格活用・未然形 |
| む | 仮定の助動詞・連体形 |
| に | 格助詞 |
| は、 | 係助詞 |
| 仏 | ー |
| だに | 副助詞 |
| よく | 副詞 |
| かき | カ行四段活用・連用形 |
| たてまつら | 補助動詞・ラ行四段活用・未然形・謙譲語 |
| ば、 | 接続助詞 |
| 百千 | ー |
| の | 格助詞 |
| 家 | ー |
| も | 係助詞 |
| いでき | カ行変格活用・連用形 |
| な | 強意の助動詞・未然形 |
| ん。 | 推量の助動詞・終止形 |
| わたうたち | 代名詞 |
| こそ、 | 係助詞 |
| させる | 連体詞 |
| 能 | ー |
| も | 係助詞 |
| おはせ | サ行変格活用・未然形 |
| ね | 打消の助動詞・已然形 |
| ば、 | 接続助詞 |
| もの | ー |
| を | 格助詞 |
| も | 係助詞 |
| 惜しみ | マ行四段活用・連用形 |
| たまへ。」 | 尊敬の補助動詞・ハ行四段活用・已然形 |
| と | 格助詞 |
| 言ひ | ハ行四段活用・連用形 |
| て、 | 接続助詞 |
| あざ笑ひ | ハ行四段活用・連用形 |
| て | 接続助詞 |
| こそ | 係助詞 |
| 立て | タ行四段活用・已然形 |
| り | 存続の助動詞・連用形 |
| けれ。 | 過去の助動詞・已然形 |
| そ | 代名詞 |
| の | 格助詞 |
| のち | ー |
| に | 断定の助動詞・連用形 |
| や、 | 係助詞 |
| 良秀 | ー |
| が | 格助詞 |
| よぢり不動 | ー |
| と | 格助詞 |
| て、 | 接続助詞(※「とて」で格助詞とする場合もある) |
| 今に | 副詞 |
| 人々 | ー |
| めで合へ | ハ行四段活用「めで合ふ」の已然形 |
| り。 | 存続の助動詞「り」の終止形 |
運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)
詳しいプロフィールを見る
青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。