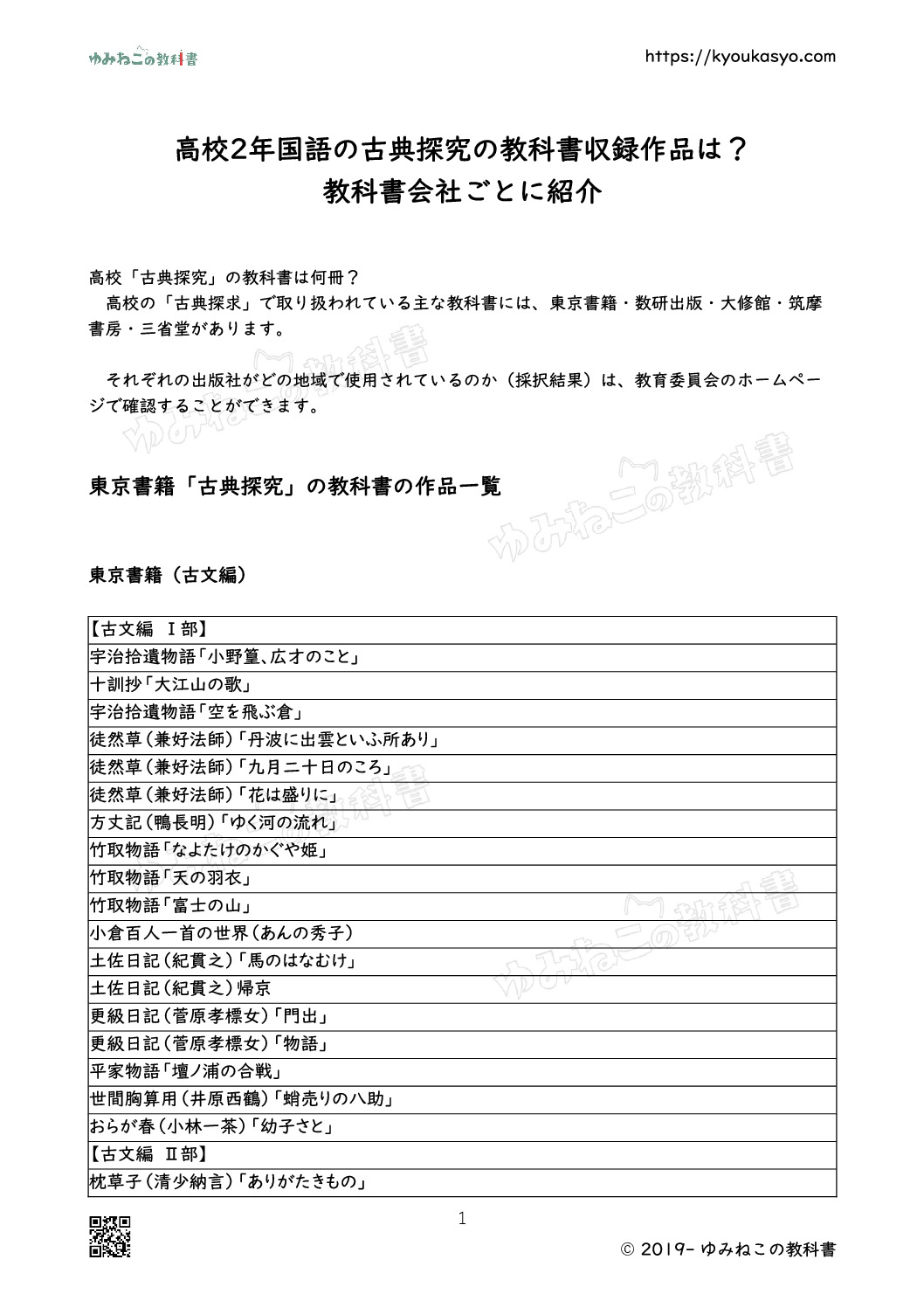高校2年国語の古典探究の教科書収録作品は?教科書会社ごとに紹介
高校で学習する「古典探究」の教科書に収録されている作品を主な教科書会社ごとに解説しています。

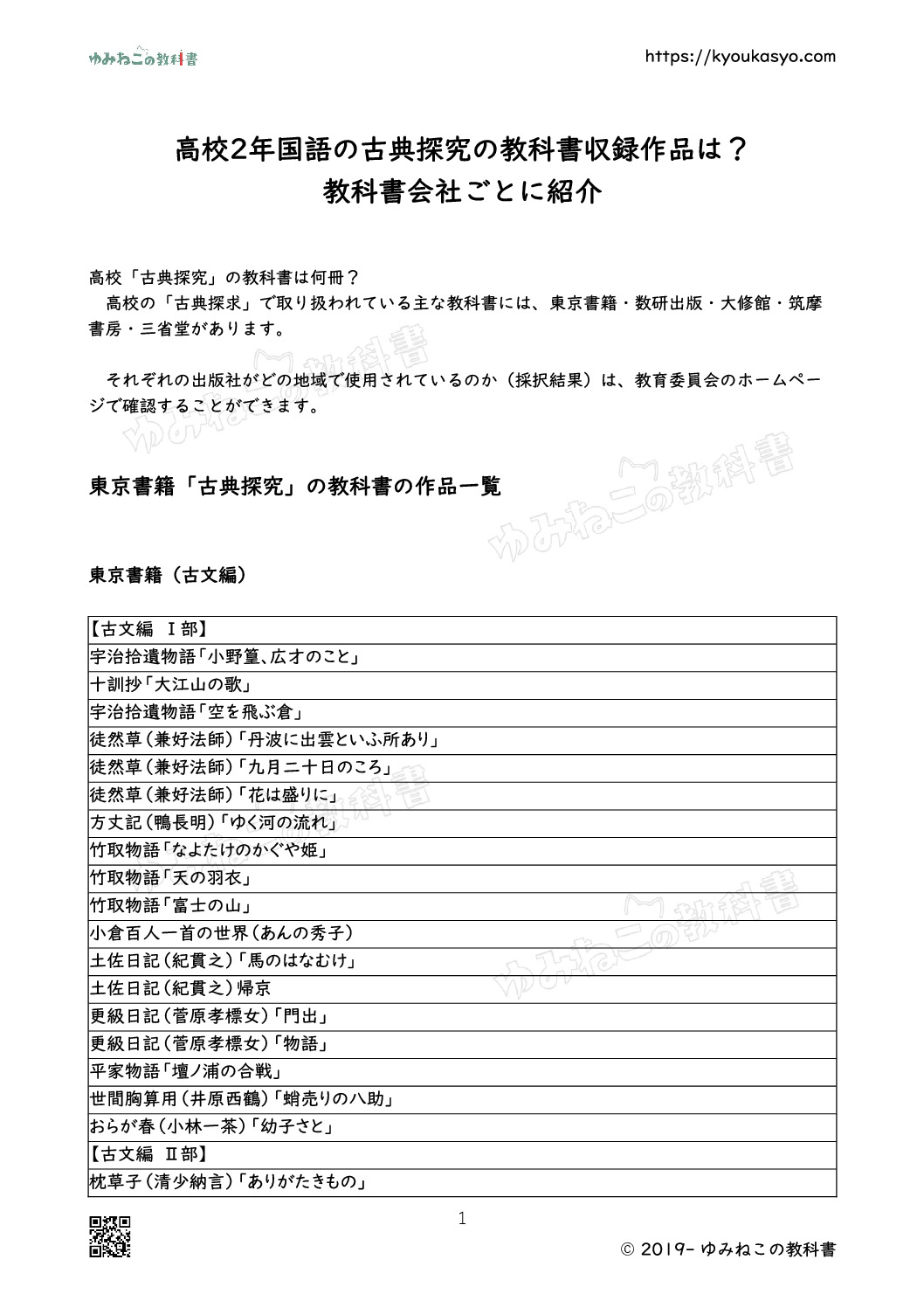
高校2年国語の古典探究の教科書収録作品は? 教科書会社ごとに紹介のPDF(19枚)がダウンロードできます。
PDFを印刷して手書きで勉強したい方は以下のボタンからお進み下さい。
無料ダウンロードページへ
高校「古典探究」の教科書は何冊?
高校の「古典探求」で取り扱われている主な教科書には、東京書籍・数研出版・大修館・筑摩書房・三省堂があります。
それぞれの出版社がどの地域で使用されているのか(採択結果)は、教育委員会のホームページで確認することができます。
→東京都の「古典探究」教科書採択結果のページ
「古典探究」の教科書の出版社ごとの収録作品は、以下のとおりとなります。
東京書籍「古典探究」の教科書の作品一覧
東京書籍(古文編)
| 【古文編 Ⅰ部】 |
| 宇治拾遺物語「小野篁、広才のこと」 |
| 十訓抄「大江山の歌」 |
| 宇治拾遺物語「空を飛ぶ倉」 |
| 徒然草(兼好法師)「丹波に出雲といふ所あり」 |
| 徒然草(兼好法師)「九月二十日のころ」 |
| 徒然草(兼好法師)「花は盛りに」 |
| 方丈記(鴨長明)「ゆく河の流れ」 |
| 竹取物語「なよたけのかぐや姫」 |
| 竹取物語「天の羽衣」 |
| 竹取物語「富士の山」 |
| 小倉百人一首の世界(あんの秀子) |
| 土佐日記(紀貫之)「馬のはなむけ」 |
| 土佐日記(紀貫之)帰京 |
| 更級日記(菅原孝標女)「門出」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「物語」 |
| 平家物語「壇ノ浦の合戦」 |
| 世間胸算用(井原西鶴)「蛸売りの八助」 |
| おらが春(小林一茶)「幼子さと」 |
| 【古文編 Ⅱ部】 |
| 枕草子(清少納言)「ありがたきもの」 |
| 枕草子(清少納言)「九月ばかり」 |
| 枕草子(清少納言)「中納言参り給ひて」 |
| 枕草子(清少納言)「雪のいと高う降りたるを」 |
| 伊勢物語「初冠(ういこうぶり)」 |
| 伊勢物語「東下り」 |
| 伊勢物語「渚の院」 |
| 大和物語「姨捨(をばすて)」 |
| 大鏡「道真の左遷」 |
| 大鏡「三船の才」 |
| 大鏡「道長、伊周の競射」 |
| 袋草紙(藤原清輔)「能因と節信」 |
| 無名抄(鴨長明)「出で映えすべき歌のこと」 |
| 古今和歌集仮名序(紀貫之)「やまと歌は」 |
| 源氏物語(紫式部)「光源氏の誕生」 |
| 源氏物語(紫式部)「若紫」 |
| 近世俳句抄「芭蕉」 |
| 近世俳句抄「蕪村」 |
| 近世俳句抄「一茶」 |
| 去来抄(向井去来) |
| 三冊子(服部土芳) |
| 古事記「倭建命」 |
東京書籍(漢文編)
| 【漢文編 Ⅰ部】 |
| 蛇足(戦国策) |
| 断腸(世説新語) |
| 知音(呂氏春秋) |
| 畏二饅一頭(五雑組) |
| 宿建徳江(孟浩然) |
| 勧酒(于武陵) |
| 静夜思(李白) |
| 磧中作(岑参) |
| 登岳陽楼(杜甫) |
| 登高(杜甫) |
| 八月十五日夜、禁中独直、対月憶元九(白居易) |
| 雑説(韓愈) |
| 桃花源記(陶潜) |
| 史記(司馬遷)「鴻門之会」 |
| 史記(司馬遷)「四面楚歌」 |
| 史記(司馬遷)「項王自刎」 |
| 出藍誉(荀子) |
| 侵官之害(韓非子) |
| 呂氏春秋「刻舟求剣」 |
| 塞扇馬(淮南子) |
| 列子「杞憂」 |
| 水魚之交 |
| 竭股肱之力 |
| 流涕斬馬謖 |
| 死諸葛走生仲達 |
| 【漢文編 Ⅱ部】 |
| 十八史略「鼓腹撃壌」 |
| 十八史略「宋襄之仁」 |
| 十八史略「燕雀安知鴻鵠之志哉」 |
| 詩経「桃夭」 |
| 楽府詩集「上邪」 |
| 飲酒(陶潜) |
| 子夜呉歌(李白) |
| 長恨歌(白居易) |
| 史記(司馬遷)「連覇・藺相如 澠池之会」 |
| 史記(司馬遷)「連覇・藺相如 刎頸之交」 |
| 論語「性相近也」 |
| 不忍人之心(孟子) |
| 人之性悪(荀子) |
| 無用之用(老子) |
| 大道廃有仁義(老子) |
| 小国寡民(老子) |
| 曳尾於塗中(荘子) |
| 聞旅雁(菅原道真) |
| 送夏目漱石之伊予(正岡子規) |
| 日本外史「所争不在米塩」 |
| 日本外史「諸将服信玄」 |
数研出版「古典探究」の教科書の作品一覧
| 【古文編 第一章】 |
| 十訓抄「大江山」 |
| 沙石集「兼盛と忠見」 |
| 古今著聞集「用枝の篳篥」 |
| 伊勢物語「初冠」 |
| 伊勢物語「通ひ路の関守」 |
| 伊勢物語「渚の院」 |
| 大和物語「をばすて山」 |
| 大和物語「鳥飼の院」 |
| 枕草子(清少納言)「春はあけぼの」 |
| 枕草子(清少納言)「すさまじきもの」 |
| 方丈記(鴨長明)「ゆく河の流れ」 |
| 方丈記(鴨長明)「養和の飢饉」 |
| 方丈記(鴨長明)「閑居の気味」 |
| 徒然草(兼好法師)「あだし野の露」 |
| 徒然草(兼好法師)「九月二十日のころ」 |
| 徒然草(兼好法師)「花は盛りに」 |
| 大鏡「雲林院の菩提講」 |
| 大鏡「花山天皇の出家」 |
| 大鏡「三船の才」 |
| 大鏡「道長の剛胆」 |
| 大鏡「南院の競射」 |
| 平家物語「忠度の都落ち」 |
| 平家物語「壇ノ浦」 |
| 平家物語「御前にて人々とも」 |
| 平家物語「大納言殿参り給ひて」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「東路の道の果て」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「物語」 |
| 源氏物語(紫式部)「光源氏誕生」 |
| 源氏物語(紫式部)「藤壺の入内」 |
| 源氏物語(紫式部)「小柴垣のもと」 |
| 建礼門院右京大夫集(建礼門院右京大夫)「なべて世の」 |
| 建礼門院右京大夫集(建礼門院右京大夫)「大原まうで」 |
| 古今和歌集仮名序(紀貫之)「やまと歌は」 |
| 古今和歌集仮名序(紀貫之)「六歌仙」 |
| 和歌・歌謡 |
| 江戸俳諧・八句 |
| 【古文編 第二章】 |
| 枕草子(清少納言)「二月のつごもりごろに」 |
| 枕草子(清少納言)「鳥の空音」 |
| 枕草子(清少納言)「宮に初めて参りたるころ」 |
| 蜻蛉日記(藤原道綱母)「父の離京」 |
| 蜻蛉日記(藤原道綱母)「うつろひたる聞く」 |
| 蜻蛉日記(藤原道綱母)「鷹」 |
| 紫式部日記(紫式部)「土御門邸の秋」 |
| 紫式部日記(紫式部)「水鳥の足」 |
| 紫式部日記(紫式部)「同僚女房評」 |
| 和泉式部日記(和泉式部)「薫る香に」 |
| 十六夜日記(阿仏尼)(阿仏尼)「鎌倉への出立」 |
| 無名草子「清少納言の紫式部」 |
| 無名草子「文」 |
| 近代秀歌「本歌取り」 |
| 無名抄(鴨長明)「俊成自賛歌のこと」 |
| 正徹物語(正徹)「独り雨聞く秋の夜すがら」 |
| 石上私淑言(本居宣長)「もののあはれを知る」 |
| 去来抄(向井去来)「行く春を」 |
| 去来抄(向井去来)「岩鼻や」 |
| 風姿花伝(世阿弥)「秘すれば花」 |
| 玉勝間(本居宣長)「師の説になづまざること」 |
| 花月草紙(松平定信)「花」 |
| 日本永代蔵「世界の借家大将」 |
| 雨月物語(上田秋成)「浅茅が宿」 |
| 源氏物語(紫式部)「車争ひ」 |
| 源氏物語(紫式部)「須磨」 |
| 源氏物語(紫式部)「明石の姫君入内」 |
| 源氏物語(紫式部)「紫の上の苦悩」 |
| 源氏物語(紫式部)「柏木と女三の宮」 |
| 源氏物語(紫式部)「紫の上の死」 |
| 源氏物語(紫式部)「浮舟」 |
| 住吉物語「継母の策謀」 |
| 大鏡「貫之と躬恒」 |
| 大鏡「道真と時平」 |
| 大鏡「村上天皇と安子」 |
| 大鏡「最後の徐目」 |
| 古今著聞集「菅原道真」 |
| 唐物語「王昭君」 |
| 【漢文編 第一章】 |
| 買履忘度(韓非子) |
| 世説新語「漱石枕流」 |
| 世説新語「華歆・王朗」 |
| 歴代名画記「画竜点睛」 |
| 説苑「江南橘為江北枳」 |
| 史記(司馬遷)「鴻門之会 剣舞」 |
| 史記(司馬遷)「鴻門之会 頭髪上指す」 |
| 史記(司馬遷)「鴻門之会 豎子、与に謀るに足らず」 |
| 史記(司馬遷)「四面楚歌」 |
| 史記(司馬遷)「項王自刎」 |
| 論語「道徳斉礼」 |
| 論語「長沮・桀溺」 |
| 不忍人之心(孟子) |
| 性善(孟子) |
| 性悪(荀子) |
| 鹿柴(王維) |
| 勧酒(于武陵) |
| 尋胡隠君(高啓) |
| 山中対酌(李白) |
| 磧中作(岑参) |
| 江南春(杜牧) |
| 澄邁駅通潮閣(蘇軾) |
| 雨中登岳陽楼望君山(黄庭堅) |
| 旅夜書懐(杜甫) |
| 黄鶴楼(崔顥) |
| 寄李儋元錫(韋応物) |
| 梅花(菅原道真) |
| 題野古島僧房壁(絶海中津) |
| 題不識庵撃機山図(頼山陽) |
| 題自画(夏目漱石) |
| 無為之治(老子) |
| 無用之用(老子) |
| 小国寡民(老子) |
| 曳尾於塗中(荘子) |
| 夢為胡蝶(荘子) |
| 木鶏(荘子) |
| 侵官之害(韓非子) |
| 漁父辞(屈原) |
| 桃花源記(陶淵明) |
| 売油翁(欧陽脩) |
| 【漢文編 第二章】 |
| 呂氏春秋「知音」 |
| 後漢書「梁上君子」 |
| 世説新語「三横」 |
| 捜神記「売鬼」 |
| 本事詩「人面桃花」 |
| 聊斎志異「酒虫」 |
| 閱微草堂筆記「落雷裁判」 |
| 詩経「桃夭」 |
| 飲酒(陶淵明) |
| 石壕吏(杜甫) |
| 長恨歌(白居易) |
| 史記(司馬遷)「伯夷・叔斉 首陽山に餓死す」 |
| 史記(司馬遷)「伯夷・叔斉 天道是か非か」 |
| 史記(司馬遷)「連覇・藺相如 璧を趙に帰さしむ」 |
| 史記(司馬遷)「連覇・藺相如 刎頸の交はり」 |
| 史記(司馬遷)「荊軻 風蕭蕭として易水寒し」 |
| 史記(司馬遷)「荊軻 図窮まりて匕首見る」 |
| 捕蛇者説(柳宗元) |
| 師説(韓愈) |
大修館「古典探究」の教科書の作品一覧
| 【古文編 Ⅰ部】 |
| 宇治拾遺物語「検非違使忠明のこと」 |
| 十訓抄「大江山いくのの道」 |
| 今昔物語(安倍晴明) |
| 徒然草(兼好法師)「家居のつきづきしく」 |
| 徒然草(兼好法師)「今日はそのことをなさんと思へど」 |
| 徒然草(兼好法師)「花は盛りに」 |
| 方丈記(鴨長明)「行く河の流れ」 |
| 方丈記(鴨長明)「安元の大火」 |
| 伊勢物語「初冠」 |
| 伊勢物語「月やあらぬ」 |
| 伊勢物語「つひにゆく道」 |
| 大和物語「をばすて」 |
| 枕草子(清少納言)「すさまじきもの」 |
| 枕草子(清少納言)「宮に初めて参りたるころ」 |
| 枕草子(清少納言)「中納言参り給ひて」 |
| 源氏物語(紫式部)「光源氏の誕生」 |
| 源氏物語(紫式部)「藤壺の入内」 |
| 源氏物語(紫式部)「若紫との出会い」 |
| 土佐日記(紀貫之)「羽根」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「門出」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「源氏の五十余巻」 |
| 十六夜日記(阿仏尼)「駿河路」 |
| 大鏡「概説」 |
| 大鏡「道真左遷」 |
| 大鏡「競べ弓」 |
| 大鏡「花山院の出家」 |
| 平家物語「忠度都落ち」 |
| 平家物語「能登殿最期」 |
| 万葉集 |
| 古今和歌集「仮名序ーやまと歌」 |
| 古今和歌集「仮名序ー六歌仙の歌」 |
| 古今和歌集「撰者の歌」 |
| 新古今和歌集 |
| 梁塵秘抄 |
| 閑吟集 |
| 【古文編 Ⅱ部】 |
| 古今著聞集「源義家、衣川にて安倍貞任と連歌のこと」 |
| 今昔j物語集「馬盗人」 |
| 枕草子(清少納言)「うれしきもの」 |
| 枕草子(清少納言)「二月のつごもりごろに」 |
| 枕草子(清少納言)「頭の弁の、職に参りたまひて」 |
| 枕草子(清少納言)「この草子、目に見え心に思ふことを」 |
| 堤中納言物語「虫めづる姫君」 |
| 大鏡「肝試し」 |
| 大鏡「鶯宿梅」 |
| 蜻蛉日記(藤原道綱母)「町の小路の女」 |
| 和泉式部日記(和泉式部)「薫る香に」 |
| 紫式部日記(紫式部)「和泉式部と清少納言」 |
| 無名草子「紫式部のこと」 |
| 源氏物語(紫式部)「葵の上と物の怪」 |
| 源氏物語(紫式部)「須磨の秋」 |
| 源氏物語(紫式部)「女三の宮と柏木」 |
| 源氏物語(紫式部)「紫の上の死」 |
| 源氏物語(紫式部)「薫と宇治の姫君」 |
| 俳句 |
| 市中の巻 |
| 三冊子(服部土芳)「不易と変化」 |
| 風姿花伝(世阿弥)「因果の花」 |
| 隅田川 |
| 難波土産「虚実皮膜の論」 |
| 曽根崎心中(近松門左衛門)「道行」 |
| 西鶴諸国ばなし「大みそかは合はぬ算用」 |
| 雨月物語(上田秋成)「浅茅が宿」 |
| 【漢文編 Ⅰ部】 |
| 知音 |
| 画竜点睛 |
| 両頭蛇 |
| 漱石枕流 |
| 糟糠之妻 |
| 塞扇馬 |
| 六里館(王維) |
| 六月二十七日望湖楼酔書(蘇軾) |
| 磧中作(岑参) |
| 峨眉山月歌(李白) |
| 早発白帝城(李白) |
| 登岳陽楼(杜甫) |
| 勧酒(于武陵) |
| 送別(杜牧) |
| 咸陽城東楼(許渾) |
| 哭晁卿衡(李白) |
| 『史記』への招待 |
| 史記(司馬遷)「鴻門の会 沛公 項王に見ゆ」 |
| 史記(司馬遷)「鴻門の会 樊噲目を瞋らして項王を視る」 |
| 史記(司馬遷)「項王の最期 四面皆楚歌す」 |
| 史記(司馬遷)「項王の最期 我 何の面目ありて之に見えん」 |
| 桃花源記(陶潜) |
| 捕蛇者説(柳宗元) |
| 論語「賢哉回也」 |
| 論語「聞斯行諸」 |
| 論語「行不由径」 |
| 不忍人之心(孟子) |
| 人之性悪(荀子) |
| 性猶湍水也(孟子) |
| 大道廃有仁義(老子) |
| 小国寡民(老子) |
| 曳尾於塗中(荘子) |
| 侵官之害(韓非子) |
| 不出門(菅原道真) |
| 桂林荘雑詠示諸生(広瀬淡窓) |
| 将東遊題壁(月性) |
| 題自画(夏目漱石) |
| 定伯売鬼(干宝) |
| 定婚店(李復言) |
| 【漢文編 Ⅱ部】 |
| 水魚の交はり |
| 死せる諸葛 生ける中達を走らす |
| 詩経「桃夭」 |
| 文選「行行重行行」 |
| 飲酒(陶潜) |
| 子夜呉歌(李白) |
| 石壕吏(杜甫) |
| 史記(司馬遷)「廉頗藺相如 刎頸の交はり」 |
| 史記(司馬遷)「荊軻 風蕭蕭として易水寒し」 |
| 史記(司馬遷)「荊軻 図窮まりて匕首見る」 |
| 師説(韓愈) |
| 春夜宴桃李園序(李白) |
| 論語「暴虎馮河」 |
| 論語「過猶不及」 |
| 兵者、不祥之器(老子) |
| 兼相愛(墨子) |
| 母之愛子也(韓非子) |
| 夢為蝴蝶(荘子) |
| 概説 |
| 長恨歌(白居易) |
| 人虎伝(李景亮)「才を恃みて倨傲なり」 |
| 人虎伝(李景亮)「道に虎有り」 |
| 人虎伝(李景亮)「化して異獣と為り人に靦づる有り」 |
| 人虎伝(李景亮)「我 将に託する所有らんとす」 |
| 人虎伝(李景亮)「再び此の途に遊ぶこと無かれ」 |
筑摩書房「古典探究」の教科書の作品一覧
| 【古文編 第一部】 |
| 宇治拾遺物語「袴垂、保昌にあふこと」 |
| 宇治拾遺物語「猟師、仏を射ること」 |
| 古今著聞集「刑部卿敦兼と北の方」 |
| 伊勢物語「初冠」 |
| 伊勢物語「月やあらぬ」 |
| 伊勢物語「行く蛍」 |
| 伊勢物語「狩りの使ひ」 |
| 伊勢物語「渚の院」 |
| 伊勢物語「小野の雪」 |
| 伊勢物語「とみの文」 |
| 伊勢物語「つひにゆく」 |
| 大和物語「姥捨」 |
| 大和物語「鹿の声」 |
| 枕草子(清少納言)「春は、あけぼの」 |
| 枕草子(清少納言)「野分のまたの日こそ」 |
| 枕草子(清少納言)「文ことばなめき人こそ」 |
| 枕草子(清少納言)「よのなかになほいと心憂きものは」 |
| 枕草子(清少納言)「二月のつごもりごろに」 |
| 堤中納言物語「虫めづる姫君」 |
| 落窪物語「落窪の君」 |
| 源氏物語(紫式部)「光源氏の誕生」 |
| 源氏物語(紫式部)「飽かぬ別れ」 |
| 源氏物語(紫式部)「廃院の怪」 |
| 源氏物語(紫式部)「若紫の君」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「継母との別れ」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「継母との別れ」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「源氏の五十余巻」 |
| 蜻蛉日記(藤原道綱母)「嘆きつつ」 |
| 蜻蛉日記(藤原道綱母)「道綱鷹を放つ」 |
| 徒然草(兼好法師)「大事を思ひ立たむ人は」 |
| 徒然草(兼好法師)「世に語り伝ふること」 |
| 徒然草(兼好法師)「筑紫に、なにがしの押領使など」 |
| 徒然草(兼好法師)「これも仁和寺の奉仕」 |
| 徒然草(兼好法師)「九月二十日のころ」 |
| 徒然草(兼好法師)「久しく隔たりて会ひたる人の」 |
| 方丈記(鴨長明)「安元の大火」 |
| 方丈記(鴨長明)「養和の飢饉」 |
| 大鏡「雲林院の菩提講」 |
| 大鏡「花山院の出家」 |
| 大鏡「公任、三船の誉れ」 |
| 大鏡「南の院の競射」 |
| 風姿花伝(世阿弥)「二十四、五」 |
| 難波土産「虚実皮膜の論」 |
| 謡曲「忠度」 |
| 万葉の歌 |
| 王家の歌 |
| 中世の歌 |
| 近世の句 |
| おらが春(小林一茶)「愛児さと」 |
| 【古文編 第二部】 |
| 今昔物語「鷲にさらわれた赤子」 |
| 今昔物語「賀茂の祭りを見物する翁」 |
| 枕草子(清少納言)「里にまかでたるに」 |
| 枕草子(清少納言)「上にさぶらふ御猫は」 |
| 源氏物語(紫式部)「車争ひ」 |
| 源氏物語(紫式部)「心づくしの秋」 |
| 源氏物語(紫式部)「母子の別離」 |
| 源氏物語(紫式部)「暁の雪」 |
| 源氏物語(紫式部)「萩のうは露」 |
| 源氏物語(紫式部)「霧の中のかいま見」 |
| 源氏物語(紫式部)「髪の香」 |
| 『源氏物語』の虚構(鈴木日出男) |
| 紫式部日記(紫式部)「土御門殿の秋」 |
| 紫式部日記(紫式部)「和泉式部と清少納言」 |
| 和泉式部日記(和泉式部)「夢よりもはかなき世の中」 |
| 建礼門院右京大夫集(建礼門院右京大夫)「なべて世の」 |
| 十六夜日記(阿仏尼)「関の藤川」 |
| 古今和歌集仮名序(紀貫之)「やまとうたは」 |
| 古今和歌集仮名序(紀貫之)「六歌仙」 |
| 俊頼髄脳(源俊頼)「連歌」 |
| 無名抄(鴨長明)「おもて歌」 |
| 毎月抄(藤原定家)「心と詞」 |
| 無名草子「紫式部」 |
| 大鏡「菅公配流」 |
| 大鏡「宣耀殿の女御」 |
| 大鏡「中宮安子の嫉妬」 |
| 大鏡「肝試し」 |
| 大鏡「道長、栄華への第一歩」 |
| 増鏡「後鳥羽院」 |
| 増鏡「隠岐配流」 |
| 野ざらし紀行(松尾芭蕉)「千里に旅立ちて」 |
| 去来抄(向井去来)「行く春を」 |
| 去来抄(向井去来)「岩鼻や」 |
| いそのはな(与謝蕪村)「北寿老仙をいたむ」 |
| 鶉衣(横井也有)「奈良団扇」 |
| 西鶴諸国ばなし(井原西鶴)「忍び扇の長歌」 |
| 雨月物語(上田秋成)「浅茅が宿」 |
| 三冊子(服部土芳)「不易流行」 |
| 玉勝間(本居宣長)「師の説になづまざること」 |
| 源氏物語玉の小櫛「もののあはれ論」 |
| 古事記「倭建命」 |
| 【漢文編 第一部】 |
| 呂氏春秋「知音」 |
| 曳尾於塗中(荘子) |
| 戦国策「先従隗始」 |
| 漁父辞(屈原) |
| 陶淵明集(陶淵明)「桃花源記」 |
| 春夜宴桃李園序(李白) |
| 独坐敬亭山(李白) |
| 登楽遊原(李商隠) |
| 九月九日憶山東兄弟(王維) |
| 芙蓉楼送辛漸(王昌齢) |
| 楓橋夜泊(張継) |
| 野望(王績) |
| 旅夜書懐(杜甫) |
| 八月十五夜、禁中独直、対月憶元九(白居易) |
| 遊山西村(陸游) |
| 聞旅雁(菅原道真) |
| 即事(新井白石) |
| 無題(夏目漱石) |
| 史記(司馬遷)「天道是邪、非邪」 |
| 史記(司馬遷)「鴻門之会」 |
| 史記「四面楚歌」 |
| 近古史談「稲葉一徹」 |
| 捜神記「鶴之報恩」 |
| 捜神記「売鬼」 |
| 西京雑記「王昭君」 |
| 師説(韓愈) |
| 捕蛇者説(柳宗元) |
| 愛蓮説(周敦頤) |
| 論語 |
| 人無有不善(孟子) |
| 四端(孟子) |
| 性悪(荀子) |
| 【漢文編 第二部】 |
| 世説新語「断腸」 |
| 荘子・淮南子「蟷螂の斧」 |
| 列子「愚公移山」 |
| 詩経「詩経大序」 |
| 論文(曹丕) |
| 五柳先生伝(陶淵明) |
| 前赤壁賦(蘇軾) |
| 詩経「桃夭」 |
| 秋風辞(武帝) |
| 楽府詩集「薤露」 |
| 飲酒 其五(陶淵明) |
| 送別(王維) |
| 漁翁(柳宗元) |
| 石壕吏(杜甫) |
| 長恨歌(白居易) |
| 史記「怒髪上衝冠」 |
| 史記「刎頸之交」 |
| 史記「国士無双」 |
| 日本外史「信玄何在」 |
| 太平広記「離魂記」 |
| 本事詩「人面桃花」 |
| 前出師表(諸葛亮) |
| 白氏文集(白居易)「与微之書」 |
| 傷仲永(王安石) |
| 無之用(老子) |
| 柔之勝剛(孟子) |
| 混沌(荘子) |
| 無用之用(荘子) |
| 守業(韓非子) |
| 嬰逆鱗(韓非子) |
| 兼愛(墨子) |
| 足責(墨子) |
| 言と黙(興膳宏) |
三省堂「古典探究」の教科書の作品一覧
| 【古文編 第一部】 |
| 古典を読むということ(竹西寛子) |
| 宇治拾遺物語「小野篁、広才のこと」 |
| 古今著聞集「大江山」 |
| 徒然草(兼好法師)「あだし野の露消ゆる時なく」 |
| 徒然草(兼好法師)「悲田院の尭蓮上人は」 |
| 徒然草(兼好法師)「世に従はん人は」 |
| 徒然草(兼好法師)「花は盛りに」 |
| 方丈記(鴨長明)「ゆく河の流れ」 |
| 方丈記(鴨長明)「安元の大火」 |
| 方丈記(鴨長明)「日野山の閑居」 |
| 竹取物語「かぐや姫の昇天」 |
| 伊勢物語「初冠」 |
| 伊勢物語「筒井筒」 |
| 伊勢物語「月やあらぬ」 |
| 伊勢物語「小野の雪」 |
| 大和物語「姥捨」 |
| 枕草子(清少納言)「すさまじきもの」 |
| 枕草子(清少納言)「中納言参り給ひて」 |
| 枕草子(清少納言)「雪のいと高う降りたるを」 |
| 源氏物語(紫式部)「光源氏の誕生」 |
| 源氏物語(紫式部)「藤壺の入内」 |
| 源氏物語(紫式部)「北山の垣間見」 |
| 大鏡「雲林院の菩提講」 |
| 大鏡「花山院の出家」 |
| 大鏡「弓争ひ」 |
| 大鏡「三舟の才」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「あこがれ」 |
| 更級日記(菅原孝標女)「源氏の五十余巻」 |
| 建礼門院右京大夫集(建礼門院右京大夫)「なべて世のはかなきことを」 |
| 平家物語「忠度の都落ち」 |
| 平家物語「能登殿最期」 |
| 古事記「倭建の東征」 |
| 和歌十六首 |
| 俳諧二十句 |
| 【古文編 第二部】 |
| 愛づ――虫愛づる姫君(中村桂子) |
| 枕草子(清少納言)「木の花は」 |
| 枕草子(清少納言)「宮に初めて参りたるころ」 |
| 枕草子(清少納言)「二月つごもりごろに」 |
| 枕草子(清少納言)「大納言殿参り給ひて」 |
| 大鏡「道真と時平」 |
| 大鏡「最後の除目」 |
| 大鏡「肝試し」 |
| 大鏡「道長と詮子」 |
| 蜻蛉日記(藤原道綱母)「うつろひたる菊」 |
| 蜻蛉日記(藤原道綱母)「鷹を放つ」 |
| 和泉式部日記(和泉式部)「夢よりもはかなき世の中を」 |
| 紫式部日記(紫式部)「秋のけはひ」 |
| 紫式部日記(紫式部)「和泉式部と清少納言」 |
| 俊頼髄脳(源俊頼)「沓冠折句の歌」 |
| 無名抄(鴨長明)「深草の里」 |
| 毎月抄(藤原定家)「心と詞」 |
| 正徹物語(正徹)「一字の違ひ」 |
| 去来抄(向井去来)「行く春を」 |
| 去来抄(向井去来)「岩鼻や」 |
| 源氏物語(紫式部)「物の怪の出現」 |
| 源氏物語(紫式部)「心づくしの秋風」 |
| 源氏物語(紫式部)「明石の君の苦悩」 |
| 源氏物語(紫式部)「女三の宮の降嫁」 |
| 源氏物語(紫式部)「萩の上露」 |
| 源氏物語(紫式部)「浮舟と匂宮」 |
| 無名草子 |
| 一文 |
| 風姿花伝(世阿弥)「下手は上手の手本」 |
| 難波土産「虚実皮膜の論」 |
| 玉勝間(本居宣長)「師の説になづまざること」 |
| 西鶴諸国ばなし(井原西鶴)「大晦日は合はぬ算用」 |
| 曽根崎心中(近松門左衛門)「道行」 |
| 南総里見八犬伝(曲亭馬琴)「芳流閣の決闘」 |
| 東海道中膝栗毛(十返舎一九) |
| 近松浄瑠璃(湯川秀樹) |
| 【漢文編 第一部】 |
| 『論語』――私の古典(高橋和巳) |
| 歴代名画記「画竜点睛」 |
| 春秋左氏伝「病入膏肓」 |
| 列子「杞憂」 |
| 淮南子「塞翁馬」 |
| 孫子「呉越同舟」 |
| 鹿柴(王維) |
| 宿建徳江(孟浩然) |
| 涼州詞(王之渙) |
| 春夜(蘇軾) |
| 送友人(李白) |
| 送僧帰日本(銭起) |
| 登高(杜甫) |
| 遊山西村(陸游) |
| 史記(司馬遷)「鴻門之会」 |
| 史記(司馬遷)「四面楚歌」 |
| 史記(司馬遷)「項王最期」 |
| 漁父辞(屈原) |
| 春夜宴桃李園序(李白) |
| 論語「子曰富与貴…」 |
| 論語「子曰道之以政…」 |
| 論語「子貢問政…」 |
| 無恒産而有恒心者(孟子) |
| 不忍人之心(孟子) |
| 荀子 |
| —人之性悪 |
| 大道廃有仁義(老子) |
| 無用之用(老子) |
| 曳尾於塗中(荘子) |
| 渾沌(荘子) |
| 桃花源記(陶潜) |
| 売鬼(干宝) |
| 自詠(菅原道真) |
| 山茶花(義堂周信) |
| 夜下墨水(服部南郭) |
| 悼亡(大沼枕山) |
| 無題(夏目漱石) |
| 送夏目漱石之伊予(正岡子規) |
| 航西日記(森鷗外) |
| 池亭記(慶滋保胤) |
| 取塩於我国(頼山陽) |
| 鶴梁文鈔(林鶴梁)「桜巒春容」 |
| 【漢文編 第二部】 |
| 『荘子』と素粒子(湯川秀樹) |
| 不死之薬(韓非子) |
| 世説新語「三横」 |
| 説苑「不顧後患」 |
| 史記(司馬遷)「「連覇と藺相如」完璧帰趙」 |
| 史記(司馬遷)「刎頸之交」 |
| 史記(司馬遷)「「荊軻」風蕭蕭兮易水寒」 |
| 史記(司馬遷)「図窮而匕首見」 |
| 詩経「桃夭」 |
| 文選「生年不満百」 |
| 秋風辞(漢武帝) |
| 飲酒(陶潜) |
| 兵車行(杜甫) |
| 長恨歌(白居易) |
| 人面桃花(孟棨) |
| 酒虫(蒲松齢) |
| 葉限(段成式) |
| 桃園結義 |
| 三往乃見 |
| 張翼徳大閙長坂橋 |
| 進遇於赤壁 |
| 股肱之力 |
| 何必曰利(孟子) |
| 性猶湍水也(孟子) |
| 青取之於藍而青於藍(荀子) |
| 天下莫柔弱於水(老子) |
| 夢為胡蝶(荘子) |
| 列子「愚公移山」 |
| 聖人不期修古(韓非子) |
| 非攻(墨子) |
| 師説(韓愈) |
| 捕蛇者説(柳宗元) |
| 赤壁賦(蘇軾) |
運営者情報
青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。
※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。