35徒然草「仁和寺にある法師」
解答・解説をみる
「日暮らし」の意味として、最も適切なものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:毎日
イ:一日中
ウ:日が暮れるまで
エ:日によって
正解は「イ」です。
「よしなし事」の意味として、最も適切なものを次の中から選びなさい。
ア:良いことや悪いこと
イ:あることないこと
ウ:とりとめもないこと
エ:意味もないこと
正解は「ウ」です。
「心うく覚えて」の意味として、最も適切なものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:心強く思われて
イ:心ぼそく思われて
ウ:残念に思われて
エ:楽しく思われて
正解は「ウ」です。
「かばかりかと心得て」の意味として、最も適切なものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:どのくらいのものかと考えて
イ:これだけのものと思い込んで
ウ:素晴らしいと感動して
エ:大変なことと納得して
正解は「イ」です。
「かばかり」の「か」は「これ」という意味。つまり、こればかり(これだけ)かと思い込んでという意味になる。
「かたへの人」の意味として、最も適切なものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:通りすがりの人
イ:極楽寺の人
ウ:仲の悪い人
エ:仲間の人
正解は「エ」です。
「ゆかしかりしかど」の意味として、最も適切なものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:おかしいと思ったが
イ:理由があると思ったが
ウ:真似しようと思ったが
エ:知りたいと思ったが
正解は「エ」です。
「先達」の意味として、最も適切なものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:先導者
イ:教師
ウ:仲間
エ:ご先祖
正解は「ア」です。
「心うく覚えて」とあるが、何に対してそのように感じているのか、正しいものを選び、カタカナで答えなさい。
ア:ただ一人で岩清水に行くこと
イ:歩いて岩清水に行くこと
ウ:岩清水に行ったことがないこと
エ:岩清水に行けないこと
正解は「ウ」です。
「年寄るまで」は「年を取るまで」や「年寄りになるまで」。「石清水」とは、「石清水八幡宮」のこと。「拝まざりければ」は「お参りしたことがないこと」。
「年ごろ思ひつること」とあるが、どのようなことを指すのか、もっとも適切なものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:石清水八幡宮をお参りすること
イ:極楽寺・高良などをお参りすること
ウ:1人で歩いて参拝すること
エ:山へ登る人を不思議に思うこと
正解は「ア」です。
「聞きしにも過ぎて、尊くこそおはしけれ」には、法師のどのような気持ちが込められているか、もっとも正しいものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:疑惑
イ:感謝
ウ:満足
エ:後悔
正解は「ウ」です。
現代語に直すと、「聞いていたよりも尊くあられた」となる。つまり、聞いていたよりも尊く、素晴らしかった」ということなので、ウの満足が正しい。
「山までは見ず」とあるが、その理由として正しいものを選び、カタカナで答えなさい。
ア:神を参拝することが本来の目的だと思ったから
イ:山頂までのぼる時間はなかったから
ウ:極楽寺・高良をみて満足したから
エ:なぜ人々が山にのぼるのか、納得がいかなかったから
正解は「ア」です。
「山までは見ず」の理由にあたるのは、「神へ参るこそ本意なれと思ひて」。「神へ参る」は「神を参拝する」。「本意なれと思ひて」は、「本来の目的と思って」や「本当の目的と思って」という意味。理由をきかれているので、「〜から」や「〜ので」などという形で答えているかどうかもポイント。
「年ごろ思ひつること…(中略)…山までは見ず。」は、誰の言葉か。本文から書き抜いて8文字で答えなさい。
正解は「仁和寺にある法師」です。
仁和寺にある法師とは、仁和寺にいる僧のこと。
「何事かありけん」とあるが、実際には何があったのか。本文から書き抜いて答えなさい。
正解は「石清水」です。
山の上にあったのは、法師の目的だった石清水八幡宮の本殿。本文では、「石清水」となっている。
筆者の感想が述べられている1文を、本文から抜き出して、最初の8文字を答えなさい。
正解は「少しのことにも、」です。
抜き出す一文は「少しのことにも、先達はあらまほしきことなり。」
この話の主題として、もっとも適切なものを次の中から選び、カタカナで答えなさい。
ア:石清水八幡宮は噂以上に尊いので、一度は参拝するべきである。
イ:長年思っていることは、機会を見つけてなしとげるべきである。
ウ:ちょっとしたことでも、案内してくれる人の存在が必要だ。
エ:参拝とは神を参ることが目的なので、寄り道をするべきではない。
正解は「ウ」です。
この話の主題は、最後の1文「少しのことにも、先達はあらまほしき事なり。」に込められている。石清水八幡宮を参拝しようとしたのに、1人で行ってしまったため、ふもとの極楽寺や高良などを見ただけで全てを見たと思い込んで帰ってしまい、山の上にある肝心の石清水八幡宮を参拝しそこねてしまったことから、ちょっとしたことでも案内をしてくれる人の存在が必要だ、ということを伝えている。
「徒然草」の作者を漢字で答えなさい。
正解は「兼好法師」です。
「徒然草」の成立した時代を答えなさい。
正解は「鎌倉時代」です。
「あやしうこそものぐるほしけれ」のように、「こそ」があるために文末の形が変化する決まりをなんというか、4文字で答えなさい。
正解は「係り結び」です。
「係り結びの法則」ともいう。学校の授業では「係結びの法則」と習っているなど、国語の先生の指導のとおりに答えた方が安全な場合があります。「係り結び」という答えは、実際のいくつかの学校のテストや、市販の参考書の問題・解答を参考にしています。そちらでは、「係り結び」だけで正解になっています。
「あやしうこそものぐるほしけれ」の「あやしう」を現代仮名遣いに直して答えなさい。
正解は「あやしゅう」です。
「徒歩より詣でけり」の「徒歩」の読みを答えなさい。
正解は「かち」です。
他の問題を解く
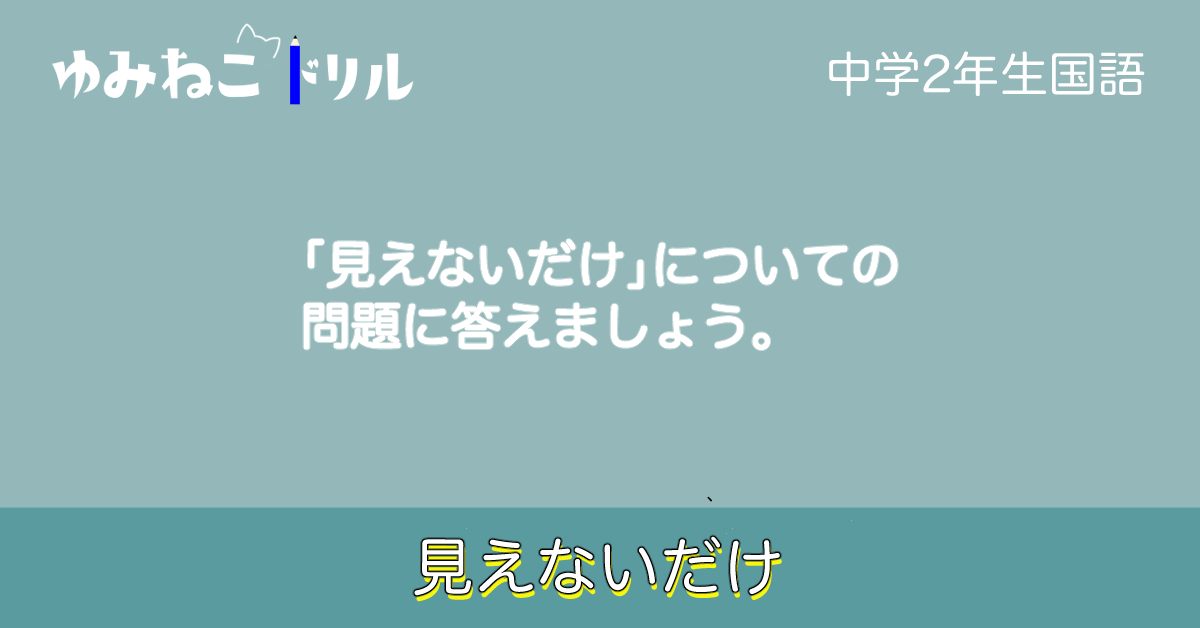 見えないだけ
見えないだけ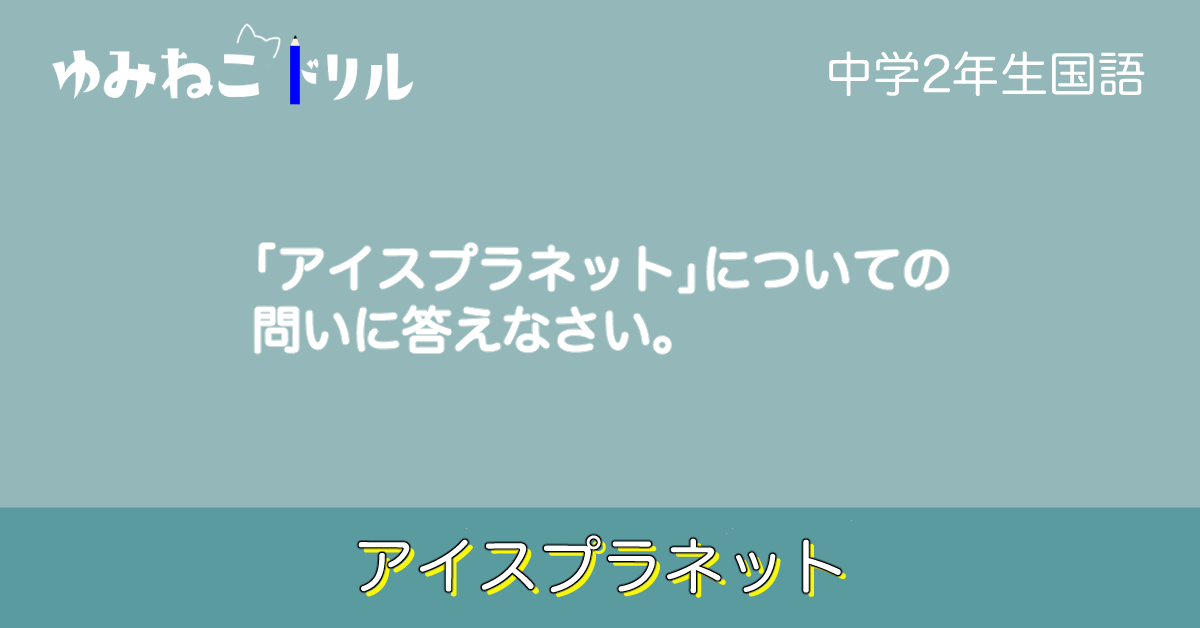 アイスプラネット
アイスプラネット- 手紙の効用
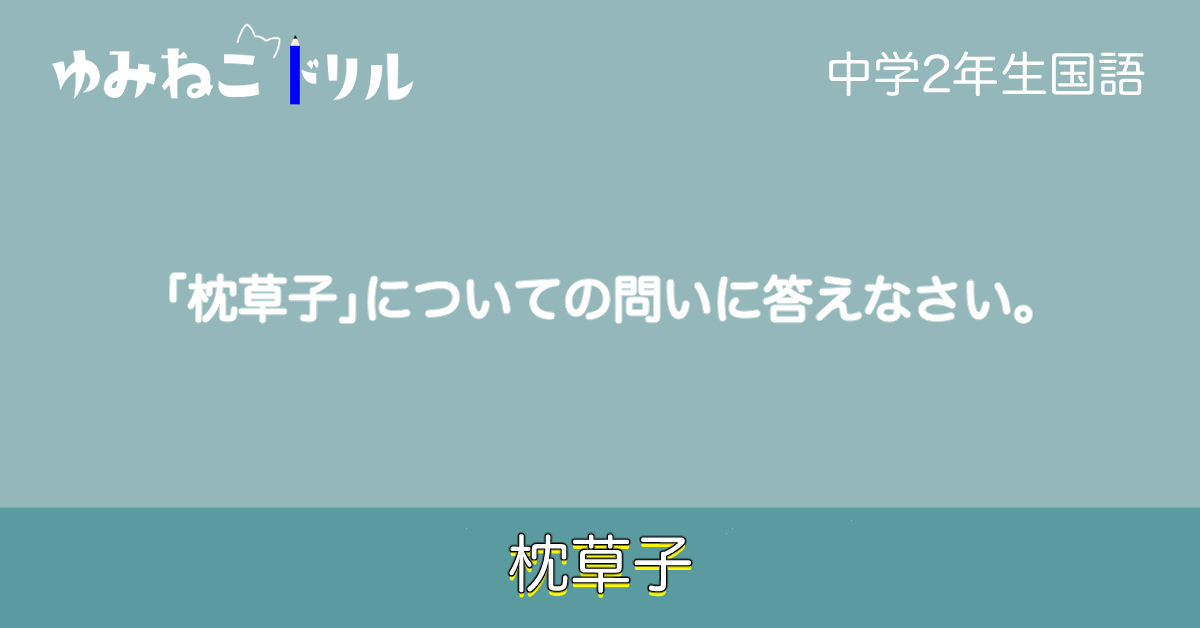 枕草子(中学校国語)
枕草子(中学校国語)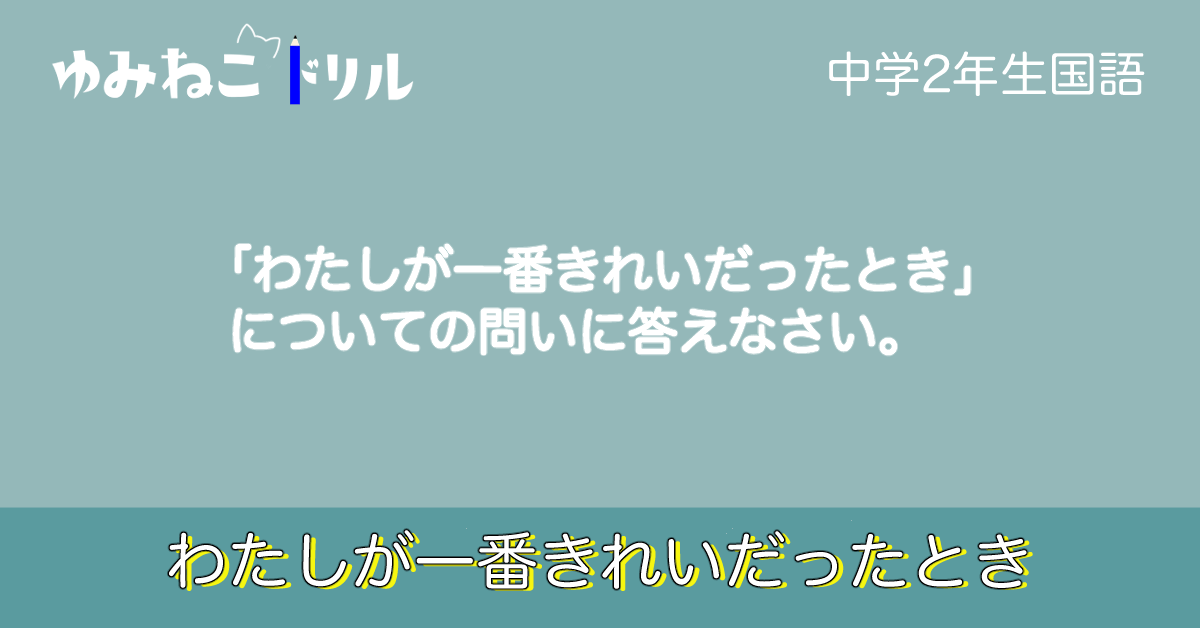 わたしが一番きれいだったとき
わたしが一番きれいだったとき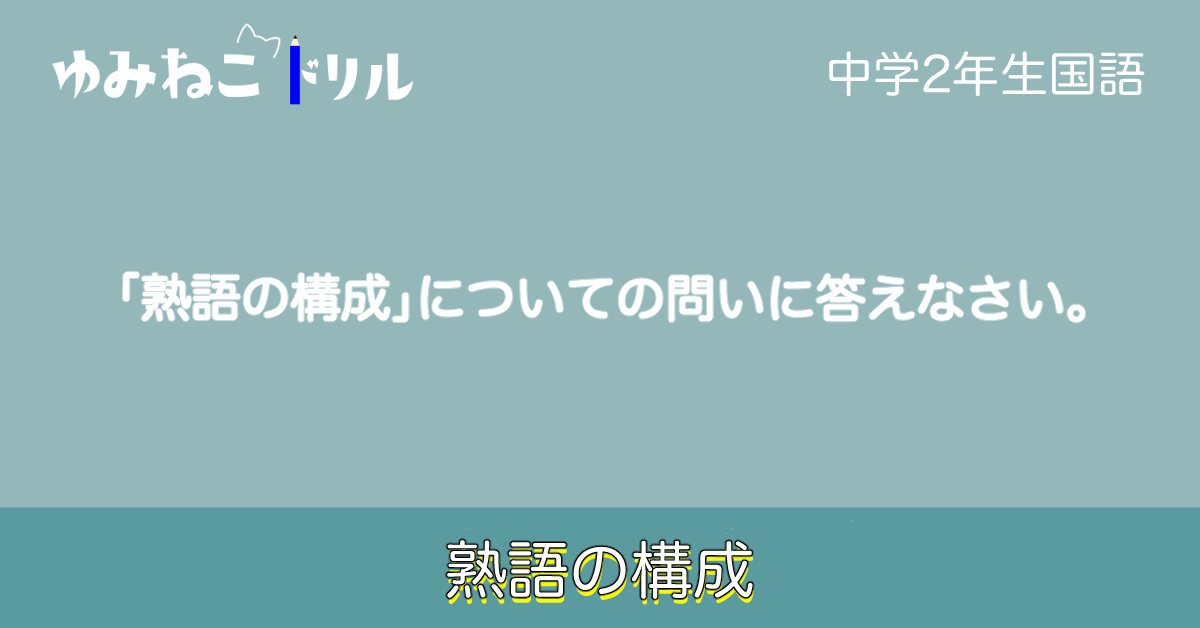 熟語の構成
熟語の構成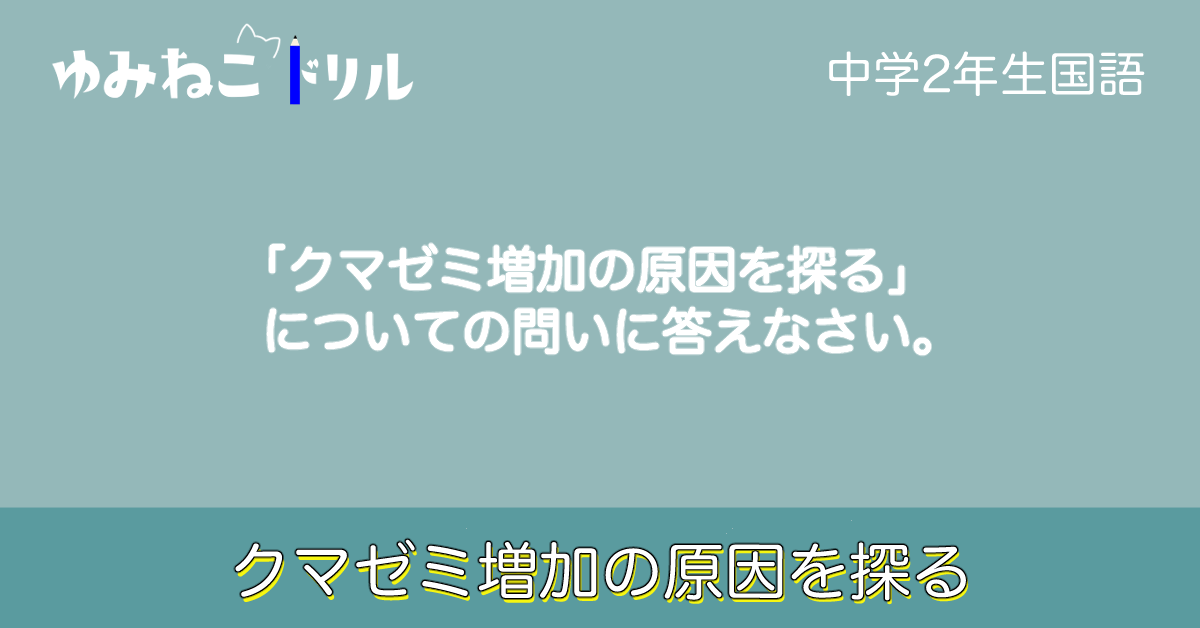 クマゼミ増加の原因を探る
クマゼミ増加の原因を探る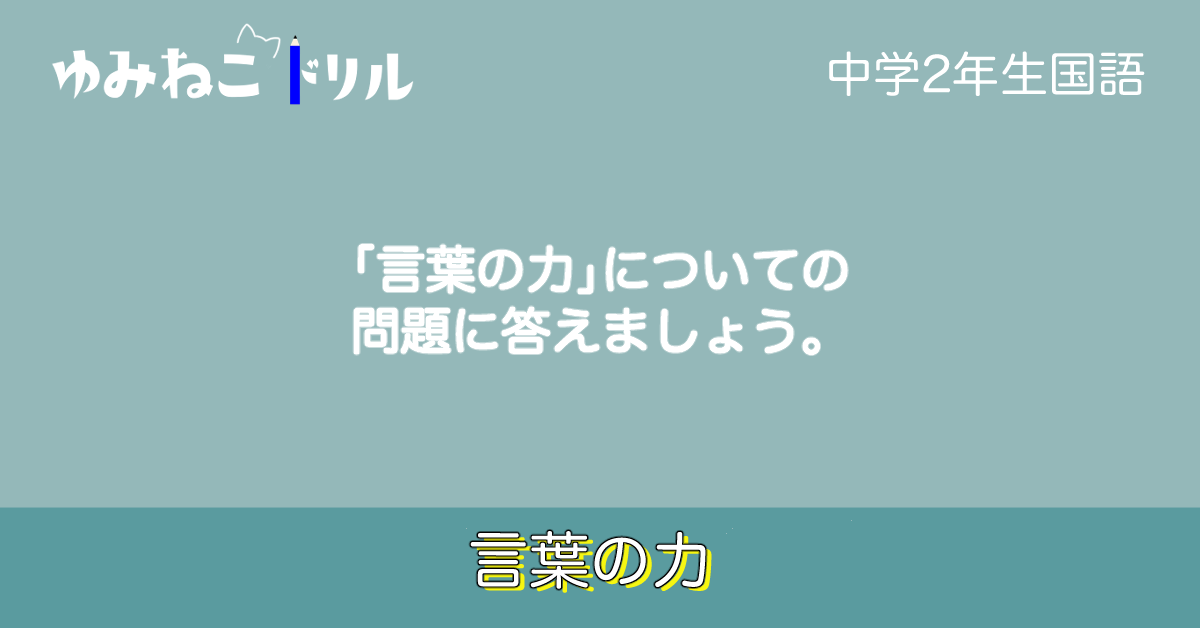 言葉の力
言葉の力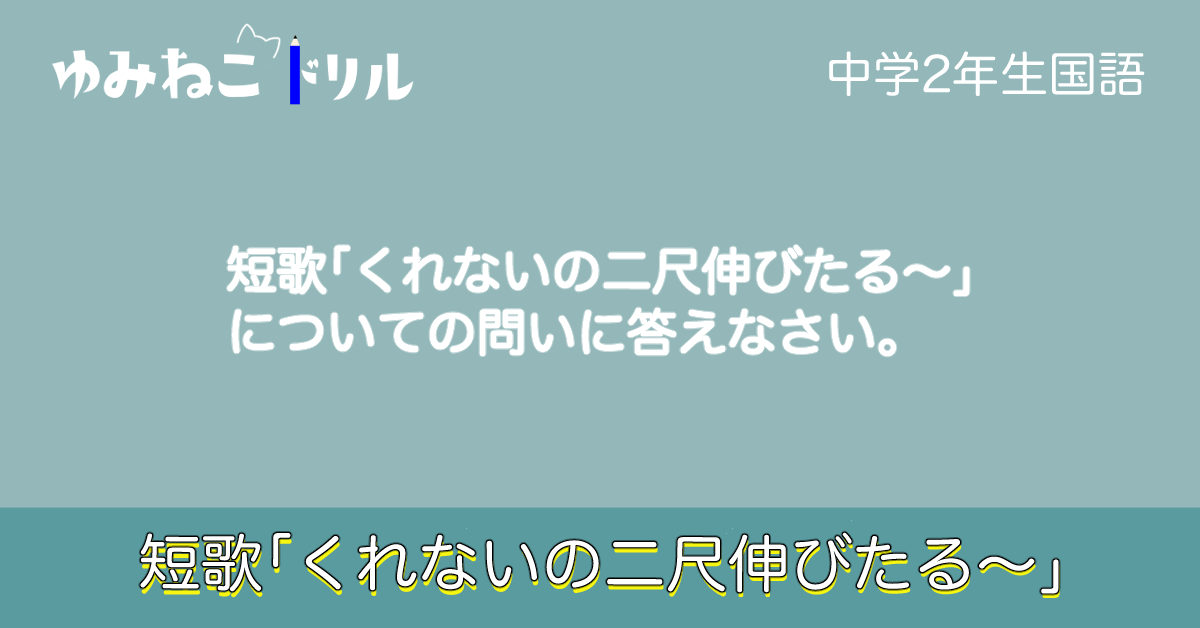 短歌「くれないの二尺伸びたる~」
短歌「くれないの二尺伸びたる~」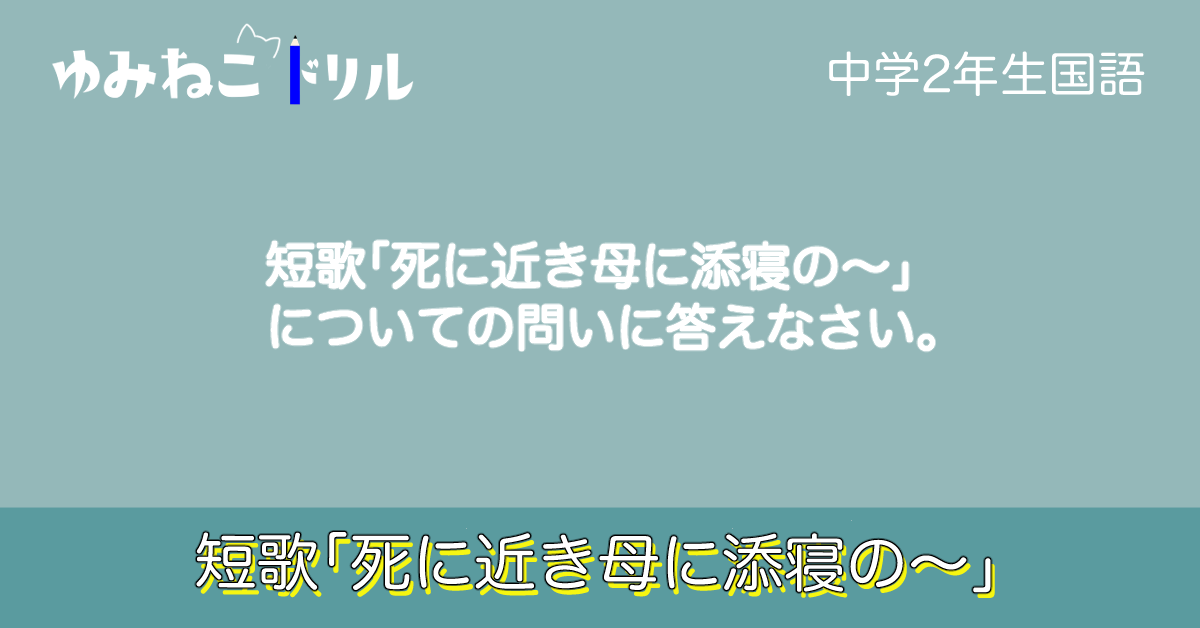 短歌「死に近き母に添寝の~」
短歌「死に近き母に添寝の~」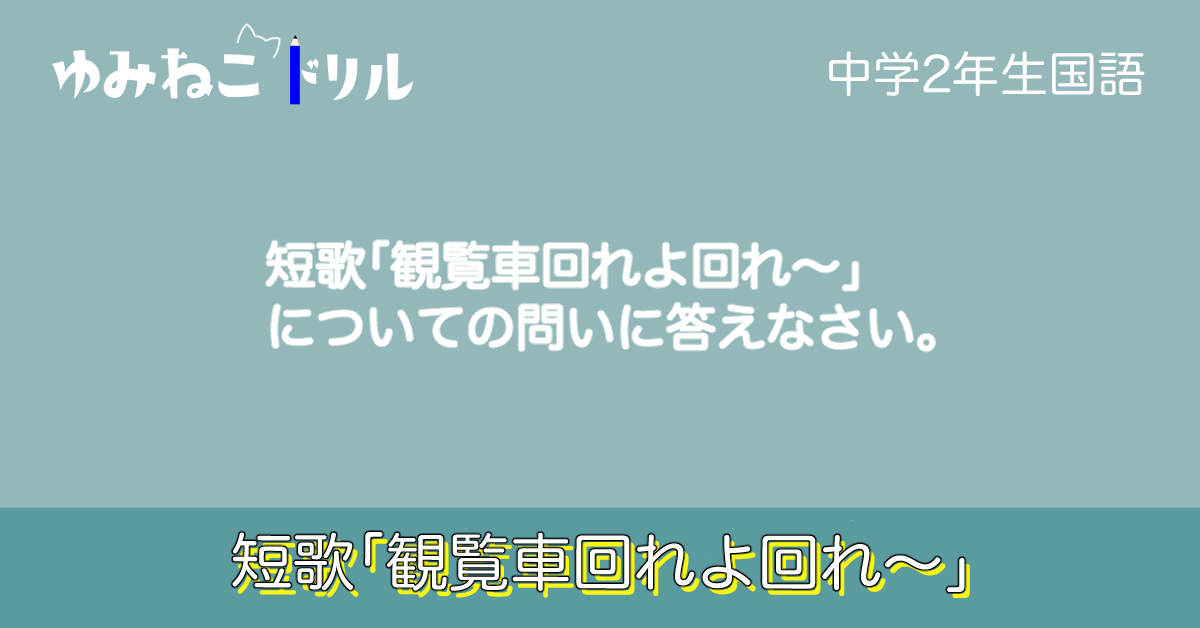 短歌「観覧車回れよ回れ~」
短歌「観覧車回れよ回れ~」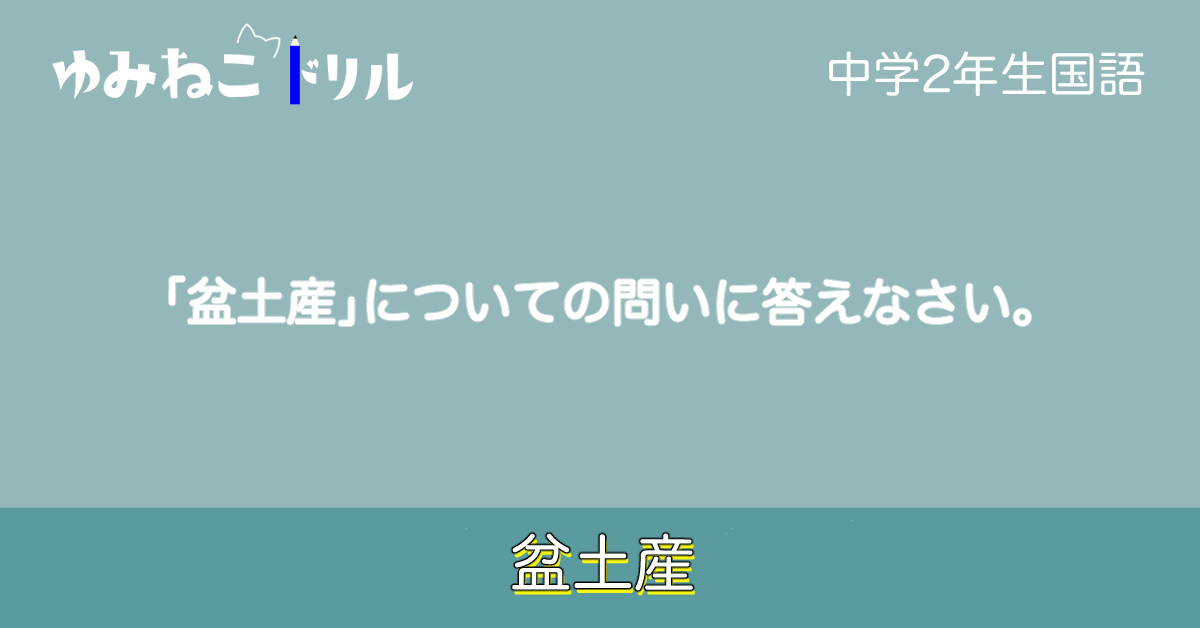 盆土産
盆土産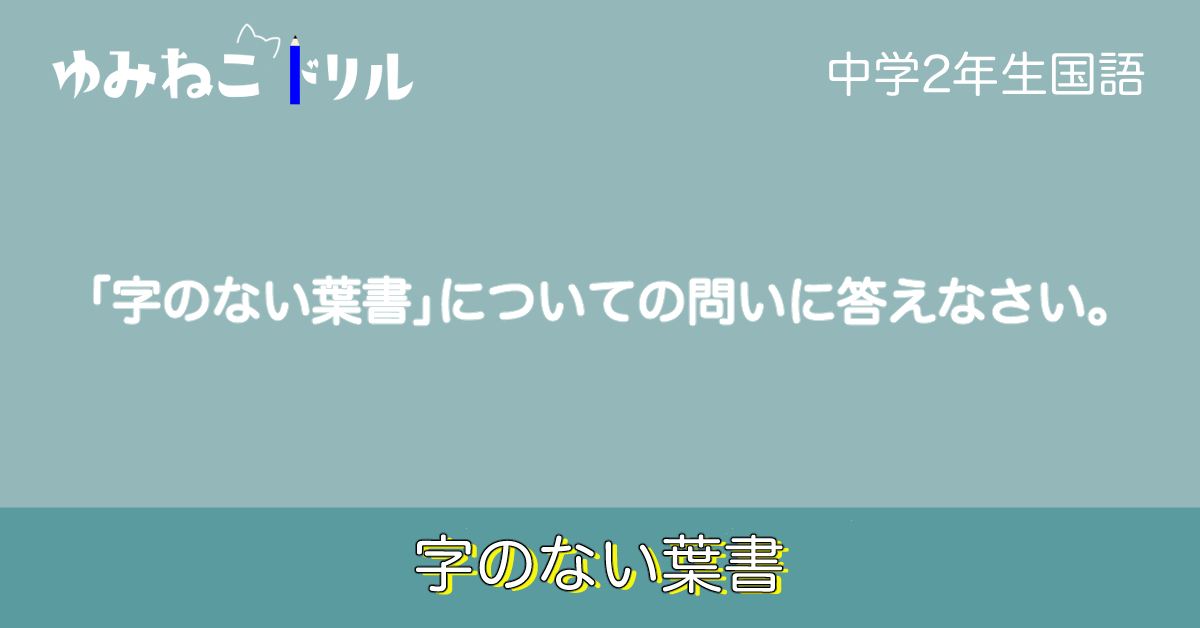 字のない葉書
字のない葉書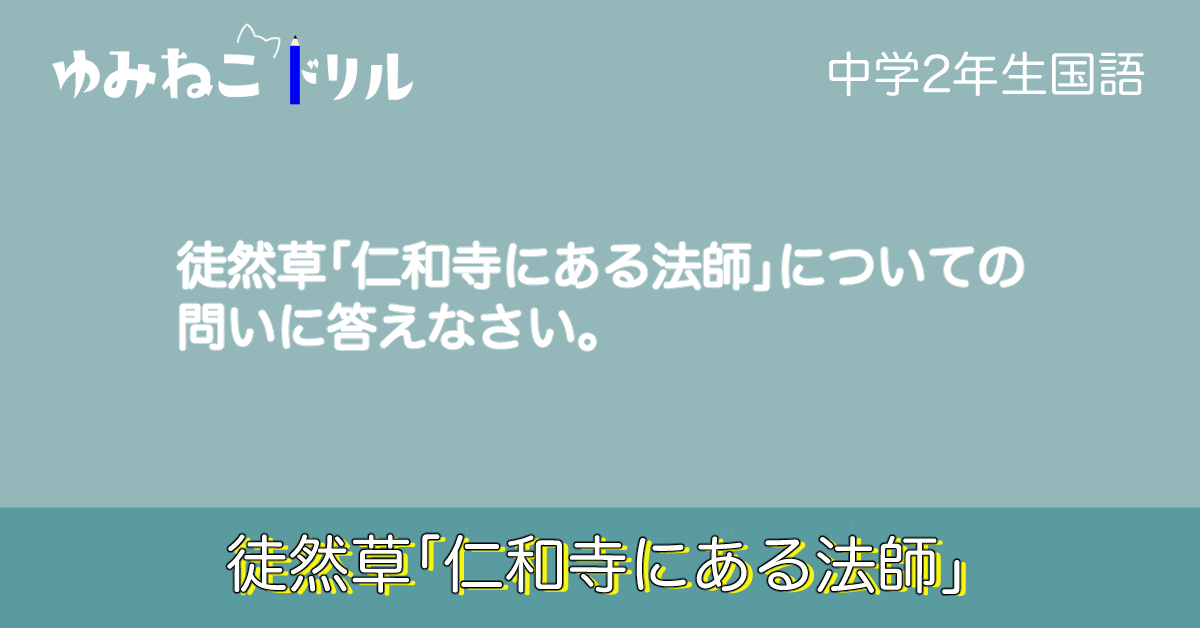 徒然草「仁和寺にある法師」
徒然草「仁和寺にある法師」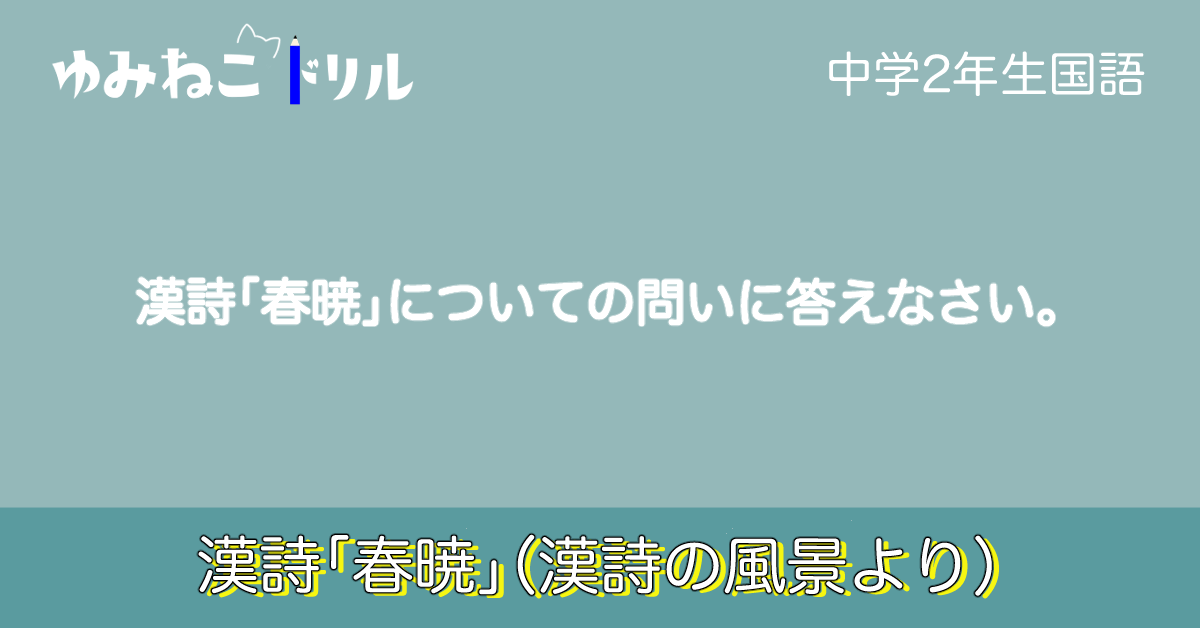 漢詩「春暁」(漢詩の風景より)
漢詩「春暁」(漢詩の風景より)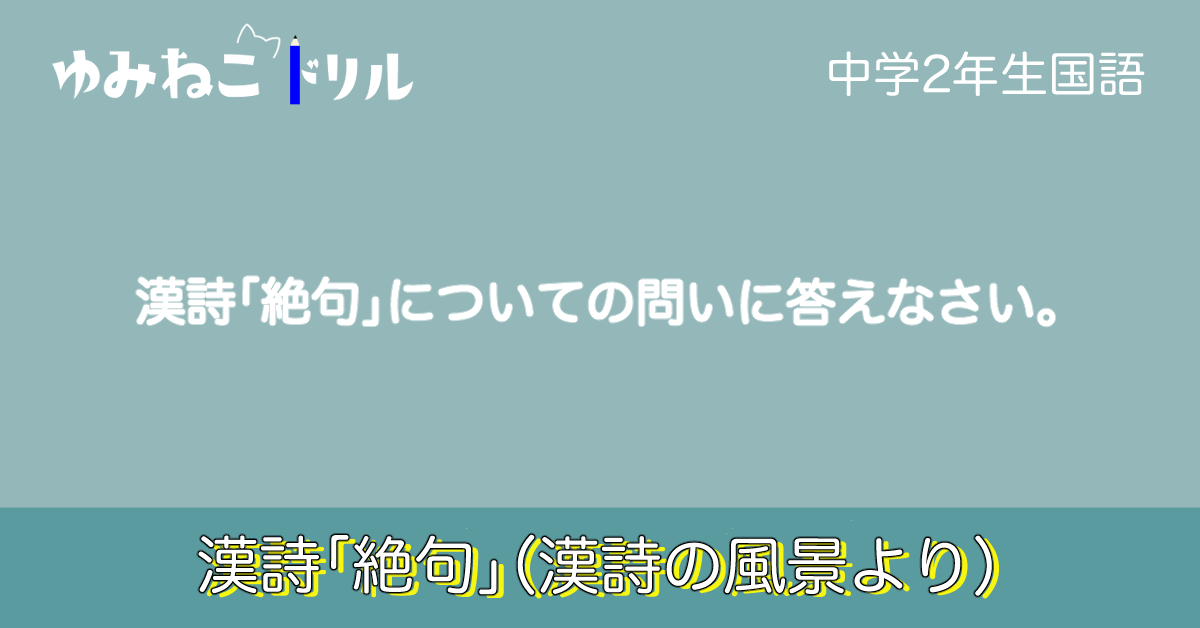 漢詩「絶句」(漢詩の風景より)
漢詩「絶句」(漢詩の風景より)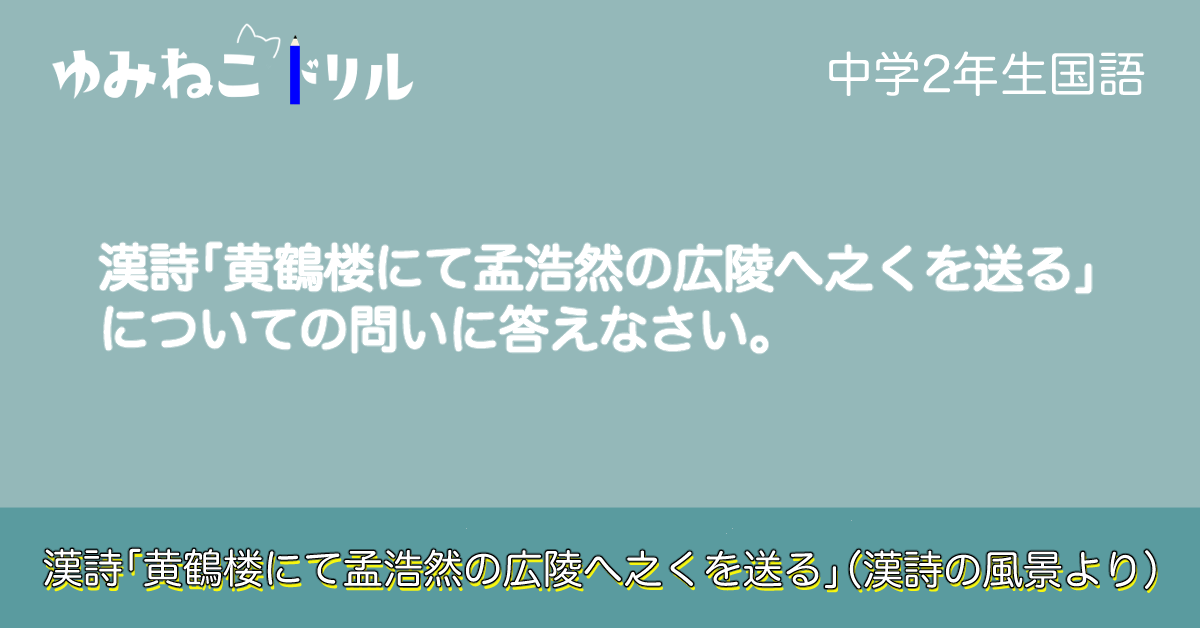 漢詩「黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る」(漢詩の風景より)
漢詩「黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る」(漢詩の風景より)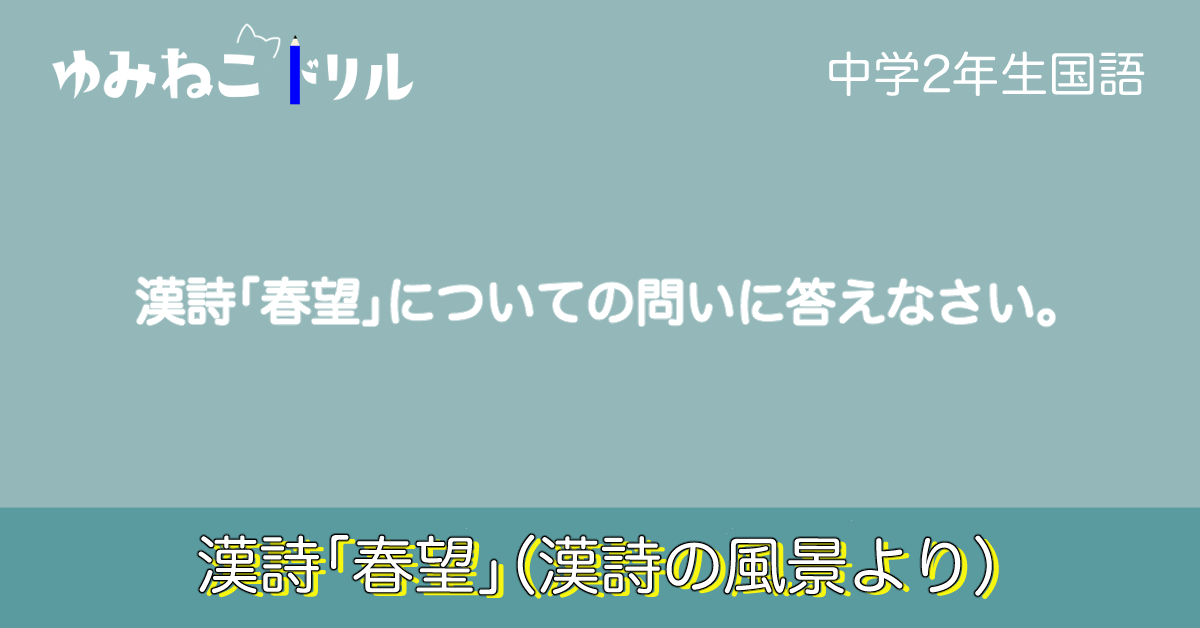 漢詩「春望」(漢詩の風景より)
漢詩「春望」(漢詩の風景より)
運営者情報

檜垣 由美子(ゆみねこ)
詳しいプロフィールを見る
青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。 ※サイト全体の運営実績についてはこちらにまとめています。