「赤とんぼ」テスト練習問題と過去問まとめ
中学音楽「赤とんぼ」について、作詞者と作曲者、曲の調や拍などの特ちょう、歌詞の意味やことばの意味など、定期テストでよく出るポイントをわかりやすく解説するよ。
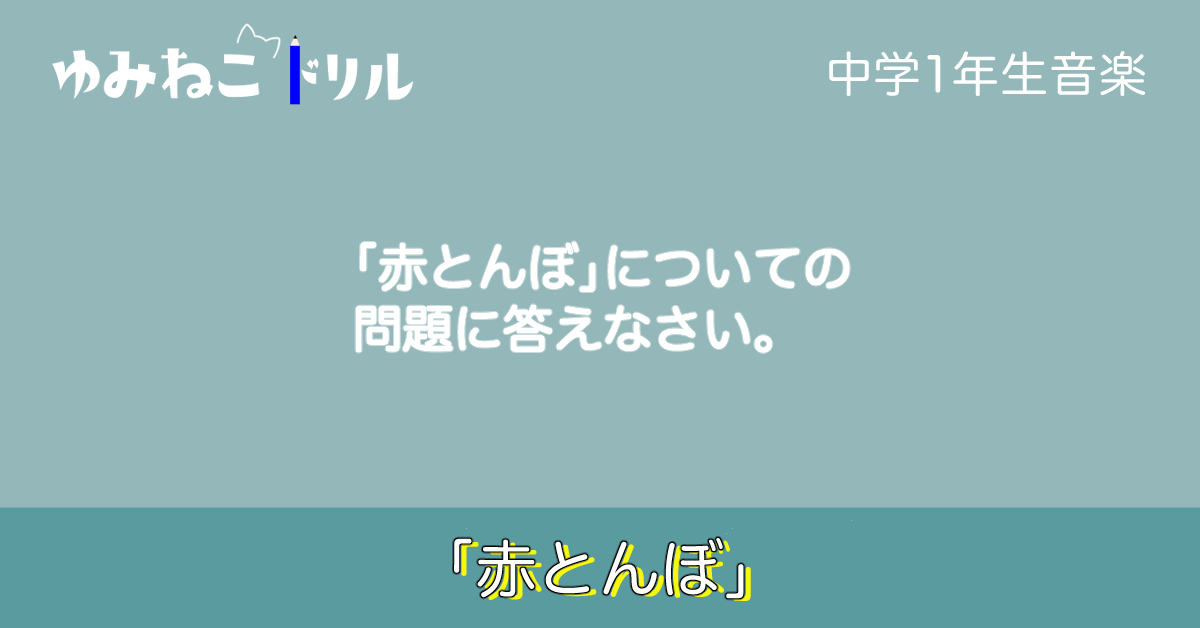
「赤とんぼ」の問題に挑戦できる自動採点機能付きのドリルもあるよ!
「赤とんぼ」の基本情報
作曲:山田耕作
拍子:4分の3拍子
調:変ホ長調
速度:♩=58〜63
形式:一部形式
「赤とんぼ」の歌詞
テストでは、歌詞の穴埋め問題が出たりするよ。
多くは一部が抜き出されるだけなので、前後の言葉の関係を覚えていれば大丈夫だけれど、「この小節の1番の歌詞をかけ」というように、1番〜4番までの歌詞の区別がついている必要や、ワンフレーズ全て答えなければいけない問題が出ることもあるので注意しよう。
赤とんぼ
1 夕やけ小やけの 赤とんぼ
負われて見たのは いつの日か
2 山の畑の 桑の実を
小籠に摘んだは まぼろしか
3 十五で姐やは 嫁に行き
お里のたよりも 絶えはてた
4 夕やけ小やけの 赤とんぼ
とまっているよ 竿の先
「赤とんぼ」は、作詞者の三木露風がまだ幼いころに、自分の家に働きに来ていた子守娘におんぶされて赤とんぼを見たときのことを思い出して作ったものだよ。
「赤とんぼ」で重要なポイントはココ!
「赤とんぼ」に登場する言葉の意味
赤とんぼの歌詞には、今ではあまり使わない言葉があるよ。
それぞれがどういう意味か理解しておこう!
「負われて見た」
負われてというのは、「背負われて」ということ。つまり、おんぶされていたということだね。
「姐や」
ねえやといっても、お姉さんのことではないよ。
昔は、あまり裕福ではないおうちの女の子は、よそのおうちに子守のお手伝いとして働きに出ることがあったんだ。
そうやって子守をする女の子のことを、姐やと呼ぶんだ。
「お里のたより」
「お里」というのは、ふるさとのこと。「たより」は手紙のこと。
ここでは、子守をするために働きに出てきた女の子のふるさとのことを言っているんだよ。
作詞をした三木露風の説明によると、
「姐やは大きくなって、里に帰り、しばらく手紙をくれていたが、15歳で嫁に行ってしまったので姐やからの手紙も来なくなった」ということだと考えられるよ(色んな説があるよ)。
「赤とんぼ」で使われている音楽記号について
P
読み方:ピアノ
意味:弱く
mf
読み方:メッツォフォルテ(メゾフォルテ)
意味:少し強く
<
読み方:クレッシェンド
意味:だんだん強く
>
読み方:デクレッシェンド
意味:だんだん弱く
「赤とんぼ」の過去と現在について
「赤とんぼ」は、1番の「夕やけ小やけの赤とんぼ」は今、目の前にいる赤とんぼのことで、その後の「負われて見たのはいつの日か」から3番までは過去の思い出のことが書かれているんだ。
4番になると、また今現在目の前にいる赤とんぼのことが書かれているよ。
1番から4番の間に、「現在→過去→現在」というように時間が動いているんだね。
「赤とんぼ」の形式について
「赤とんぼ」は、一部形式の曲だね。
一部形式というのは、8小節の大きな曲のまとまりが1つしかないもののこと。
Aメロ・Bメロというとピンとくるかな?
一部形式は、Aメロしかないということだね。
「夕やけ小やけの赤とんぼ」で4小節あって、
「負われて見たのはいつの日か」で4小節。
これで8小節の大きなカタマリになっているよ。
「赤とんぼ」の調について
「赤とんぼ」は、変ホ長調の曲。
変ホ長調というのは、主音(音階の中心となる、第一音のこと)が♭ミということ。
♭ミ ファ ソ ♭ラ ♭シ ド レ ♭ミ という音階になるということだね。
♭は ミとラとシの3つにつくよ。
「赤とんぼ」の拍子について
「赤とんぼ」は4分の3拍子の曲。
これは、1小節の中に「四分音符」が3つ分入る
という意味だね。
「赤とんぼ」の速度記号について
「赤とんぼ」の速度記号は ♩=58〜63。
これは、赤とんぼを演奏(歌う)時は,四分音符が一分間に58個から63個入るようなスピードで演奏(歌う)してね。という意味。
「赤とんぼ」では、定期テストにこんな問題が出る!
問1
「赤とんぼ」の作詞者と作曲者をそれぞれ答えなさい。
答えを見る
作詞者:三木露風
作曲者:山田耕作
問2
この曲の速度記号を次の中から選びなさい
ア:♪=58〜63
イ:♩=72〜84
ウ:♩=58〜63
エ:♪=60
答えを見る
答え:ウ
問3
この曲の調を答えなさい。
答えを見る
答え:変ホ長調
問4
この曲のように、ひとつの大きなメロディーのカタマリで構成されているものを何形式と呼ぶか、答えなさい。
答えを見る
答え:一部形式
問5
次の( )に入る歌詞を答えなさい。
1 夕やけ小やけの ( ア )
( イ )見たのは ( ウ )
2 山の畑の ( エ )
( オ )詰んだは ( カ )
3 十五で( キ )は嫁に行き
お里の( ク )も ( ケ )
4 夕やけ小やけの ( ア )
とまっているよ ( コ )
答えを見る
答え
ア:赤とんぼ
イ:負われて
ウ:いつの日か
エ:桑の実を
オ:小籠に
カ:まぼろしか
キ:姐や
ク:たより
ケ:絶えはてた
コ:竿の先
問6
歌詞の言葉の意味を、選択肢の中からそれぞれ正しいものを選びなさい。
①「負われて」
②「姐や」
③「お里のたより」
【選択肢】
ア:追いかけられて
イ:田舎からの電話
ウ:負けて
エ:お姉さん
オ:子守娘
カ:故郷からの手紙
キ:お手伝いのおばさん
ク:山からの手紙
ケ:背負われて
答えを見る
答え
①・ケ
②・オ
③・カ
問7
「赤とんぼ」について、最も正しく説明しているものを次の中から選びなさい。
ア:友達と追いかけっこをしていたときに見つけた赤とんぼについて書いている
イ:幼い頃みた赤とんぼの思い出だけについて書いている
ウ:お嫁に行ってしまった姉を寂しく思う気持ちを書いている
エ:赤とんぼを見たことで、幼いころの情景を思い出し、また目の前の赤とんぼを見ている現在について書いている
答えを見る
答え:エ
問8
この曲の調について、正しく説明しているものを次の中から選びなさい。
ア:主音は「ミ」である
イ:♯が3つついている
ウ:主音は「レ」である
エ:主音は「♭ミ」である
オ:♭が2つついている
答えを見る
答え:エ
問9
この曲を演奏するべき速度について、正しく説明しているものを次の中から選びなさい。
ア:曲全体で四分音符が58〜63個入るように演奏する
イ:曲全体で八分音符が58〜63個入るように演奏する
ウ:1分間で四分音符が58〜63個入るように演奏する
エ:1分間で八分音符が58〜63個入るように演奏する
答えを見る
答え:ウ
問10
この曲の拍子について、正しく説明しているものを次の中から選びなさい。
ア:1小節の中に八分音符が3つ分入る
イ:1小節の中に四分音符が3つ分入る
ウ:1小節の中に四分音符が4つ分入る
エ:1小節の中に八分音符が6つ分入る
答えを見る
答え:イ
中学音楽テスト「赤とんぼ」まとめ
- 作詩は三木露風
- 作曲は山田耕作
- 調は変ホ長調
- 拍子は4分の3拍子
- 演奏速度は♩=58〜63
- 形式は一部形式
- 「負われて」とは、「背負われて」ということ
- 「姐や」とは、「子守娘」のこと
- 「お里の頼り」とは、「故郷からきた手紙」のこと
- 1番の赤とんぼを見た後から、幼い頃の思い出について書かれ、4番ではまた今現在みている赤とんぼについて書かれている
- p(ピアノ)とは、「弱く」という意味
- mf(メゾフォルテ)とは、「少し強く」という意味
- <(クレッシェンド)とは、「だんだん強く」という意味
- >(デクレッシェンド)とは、「だんだん弱く」という意味
音楽の楽典テスト対策もして、高得点を狙おう!
運営者情報

ゆみねこ
詳しいプロフィールを見る
青山学院大学教育学科卒業。TOEIC795点。2児の母。2019年の長女の高校受験時、訳あって塾には行かずに自宅学習のみで挑戦することになり、教科書をイチから一緒に読み直しながら勉強を見た結果、偏差値20上昇。志望校の特待生クラストップ10位内で合格を果たす。

-
助かりました。ありがとうございます
-
明日、音楽のテストなので見ました!
分かりやすかったし、覚えられました。
テスト対策バッチリです!
ありがとうございます♪ -
ありがとうございます。
とても分かりやすくて、活用させていただいています。
これからもよろしくお願いします -
定期テスト対策。役だったです。
-
役に立ちました。
-
テスト前に見てればもっと良かったかもです(;;)
でもテスト後に答え合わせとして見れたしテストに出てこなかったことまで知れました!勉強になりました! -
勉強になりました!あと失礼します、山田耕作は山田耕筰こっちじゃないですかね?間違ってたらすいません
-
明後日定期テスト役に立ちました。
-
テスト対策になりました。
助かりました。(*^^*)
ありがとうございました。 -
まじわかりやすい
-
とても勉強になりました。テストに活かせそうです。
-
テスト

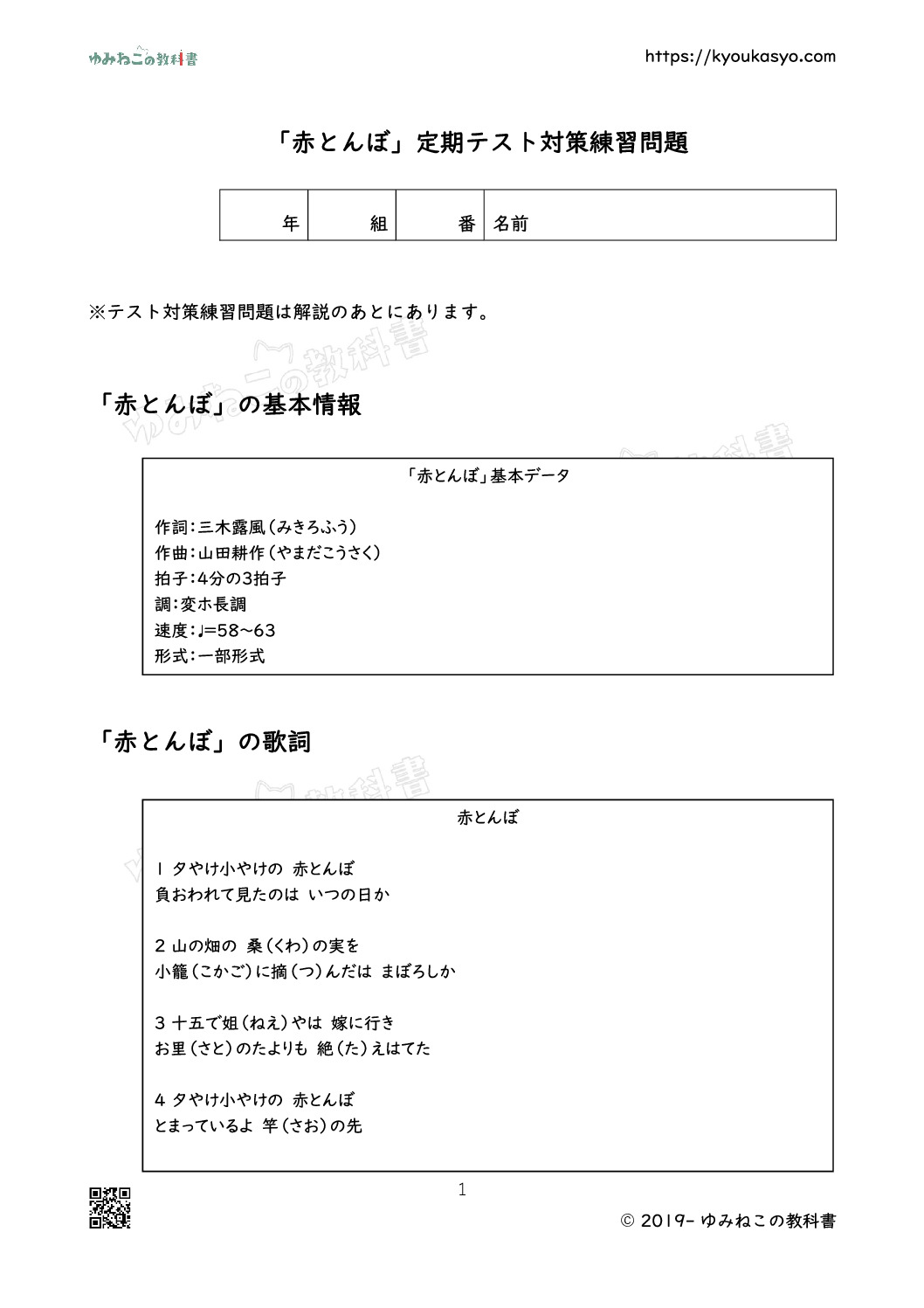

テスト対策できた。