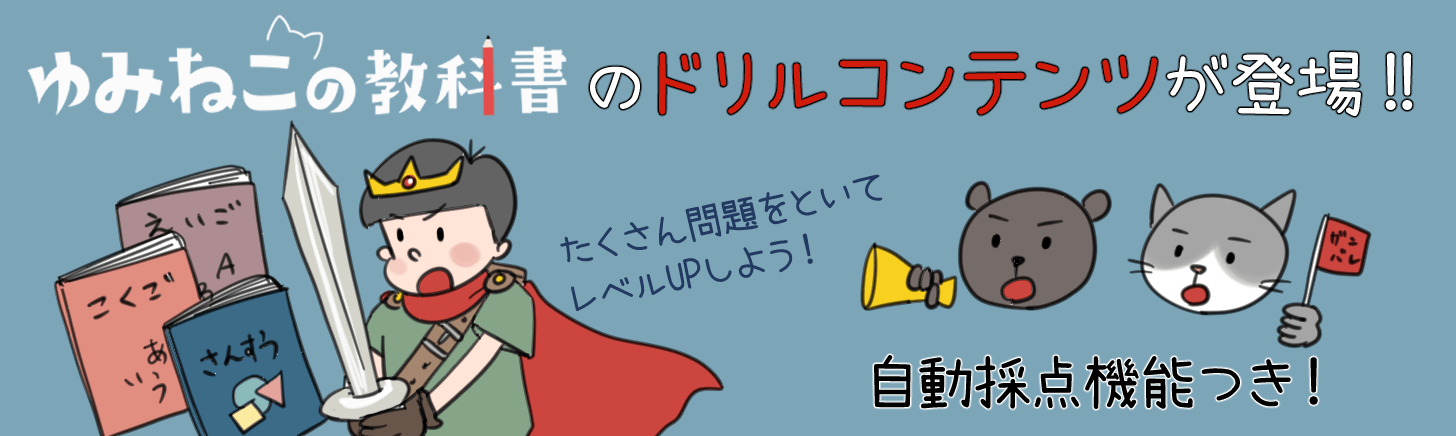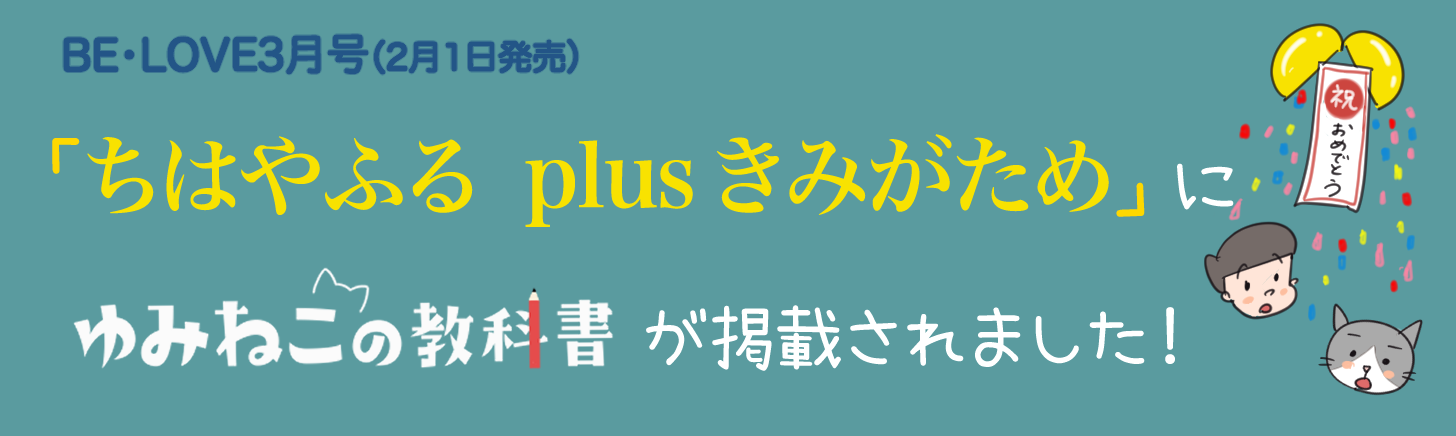閲覧数ランキング
- 井上ひさし「握手」ルロイ修道士の指言葉とは・あらすじ解説まとめ
- 「アイスプラネット」あらすじと解説「ぐうちゃんの伝えたいこと」
- 「見えないだけ(詩)」表現技法・作者の思いと伝えたいことを解説
- 「児のそら寝(ちごのそらね)」古語・現代語訳・品詞分解を解説
- 滝廉太郎「花」歌詞の意味と特徴をわかりやすく解説(テスト対策)
- 「白いぼうし(あまんきみこ)」女の子の正体は?あらすじと解説
- 「白いぼうし」テスト練習問題と過去問題まとめ
- 島崎藤村「初恋」解説と現代語訳・あらすじ(テスト対策ポイント)
- 工藤直子「野原はうたう」要点と期末テスト対策ポイントまとめ
- 「帰り道」テスト練習問題と過去問題まとめ①
- 点対称な図形の書き方(コンパスを使ったマスなしの書き方も解説)
- 歴史的仮名遣い一覧と現代仮名遣いに直すときのルール(練習問題)
- 井上ひさし「握手」テスト練習問題と過去問まとめ①
- 「加法・減法(正負の数)」計算のコツをわかりやすく解説
- 「アイスプラネット」テスト練習問題と過去問まとめ
- 因数分解「たすきがけ」を早く簡単にする裏ワザの方法を解説
- 身の回りのてこを利用した道具一覧表(力点・支点・作用点まとめ)
- 卑弥呼とはどんな人物か小学生向けにわかりやすく解説(完全版)
- 「古文重要単語」重要単語一覧と効率的な覚え方【共通テスト対策】
- 「ふきのとう(工藤直子)」無料テスト対策練習問題プリント➀
| 小学校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
| 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 |
| 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 |
| 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 |
| 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 |
| 生活 | 生活 | 生活 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 音楽 | 音楽 | 音楽 | 音楽 | 音楽 | 音楽 |
| 図画 工作 | 図画 工作 | 図画 工作 | 図画 工作 | 図画 工作 | 図画 工作 |
| 家庭 | 家庭 | 家庭 | 家庭 | 家庭 | 家庭 |
| 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
| 中学校 | ||
|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 |
| 国語 | 国語 | 国語 |
| 社会 | 社会 | 社会 |
| 数学 | 数学 | 数学 |
| 理科 | 理科 | 理科 |
| 音楽 | 音楽 | 音楽 |
| 美術 | 美術 | 美術 |
| 保健体育 | 保健体育 | 保健体育 |
| 技術・家庭 | 技術・家庭 | 技術・家庭 |
| 英語 | 英語 | 英語 |
| 高等学校 | ||
|---|---|---|
| 1年生 | 2年生 | 3年生 |
| 現代文 | 現代文 | 現代文 |
| 古典 | 古典 | 古典 |
| 世界史 | 世界史 | 世界史 |
| 日本史 | 日本史 | 日本史 |
| 地理 | 地理 | 地理 |
| 現代社会 | 現代社会 | 現代社会 |
| 倫理 | 倫理 | 倫理 |
| 政治・経済 | 政治・経済 | 政治・経済 |
| 数学 | 数学 | 数学 |
| 物理 | 物理 | 物理 |
| 化学 | 化学 | 化学 |
| 生物 | 生物 | 生物 |
| 地学 | 地学 | 地学 |
| 保健体育 | 保健体育 | 保健体育 |
| 音楽 | 音楽 | 音楽 |
| 美術 | 美術 | 美術 |
| 工芸 | 工芸 | 工芸 |
| 書道 | 書道 | 書道 |
| 英語 | 英語 | 英語 |
全学年の教科で探す
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 |
|---|---|---|
| 国語 | 国語 | 現代文 |
| 社会 | 社会 | 古典 |
| 算数 | 数学 | 世界史 |
| 理科 | 理科 | 日本史 |
| 生活 | 音楽 | 地理 |
| 音楽 | 美術 | 現代社会 |
| 図画工作 | 保健体育 | 倫理 |
| 家庭 | 技術・家庭 | 政治・経済 |
| 体育 | 英語 | 数学 |
| 物理 | ||
| 化学 | ||
| 生物 | ||
| 地学 | ||
| 保健体育 | ||
| 音楽 | ||
| 美術 | ||
| 工芸 | ||
| 書道 | ||
| 英語 |